■住民税は1年間の辛抱
1月から4月までに退職した場合、その年の5月分までの住民税は退職時に一括徴収される。私の場合は3月の給与が最後の支給であったから、そこで3か月分が徴収されたため、なかなかの減額であった(なんと住民税だけで96,000円。ふるさと納税を最大限に活用していてこの額である)。
では6月からは安くなるのかというと、そうではない。というのも、住民税というのは前年度の収入に基づいて計算されるため、あと1年はこれまでとほぼ同様の住民税を払う必要があるのである。しかも、これまでは給与から勝手に引かれていたのであまり実感はなかったが、これからは能動的にお支払いをする必要があるため、「税金を払っている」実感はより高まるであろう。
この先、定職を持たずに生活を続けて行けば、そのうち「住民税非課税世帯」になれるため、それまでの辛抱である。
■健康保険(税金とは違いますが)
健康保険の恩恵を受けるために、中途退職した場合の選択肢は、
・任意継続をする
・国民健康保険に加入する
の、いずれかとなる。どちらが良いかについては、シミュレーションサイトなどを活用して、よくよく検討しておく必要がある(「健康保険 任意継続 シミュレーション」などで検索しましょう。検索するためには自身の標準報酬月額を把握しておく必要がある。直近の標準報酬月額は、「ねんきんネット」で確認が可能)。

私の場合、仕事先が「協会けんぽ」加入であったことと、それなりの高収入であったことから、任意継続を選択した。今月以降の1か月分の保険料は36,416円であり、年間で43万越えとなかなかの金額となるが、これも1年の辛抱だと思っている(ちなみに、国民健康保険でシミュレーションをしてみたら、80万超えであった…)。今後、無収入を1年継続したら、任意継続を抜けて、国民健康保険にする予定である。
任意継続であっても、協会けんぽであるのか、それとも各会社の健康保険であるのかによっても金額が異なる(自身の年齢等も関係してくる)。しかし、大雑把にまとめると、協会けんぽに加入していて、それなりに収入が高かった場合は、任意継続が良い選択肢となる(上限に限度があるため。なお協会けんぽの任意継続の場合、標準報酬月額の上限は32万であるが、私の退職前最後の標準報酬月額は50万であった)。
なお収入だけでなく、以下にある通り、住んでいる地域によっても若干金額は異なる。
図:健康保険料率表
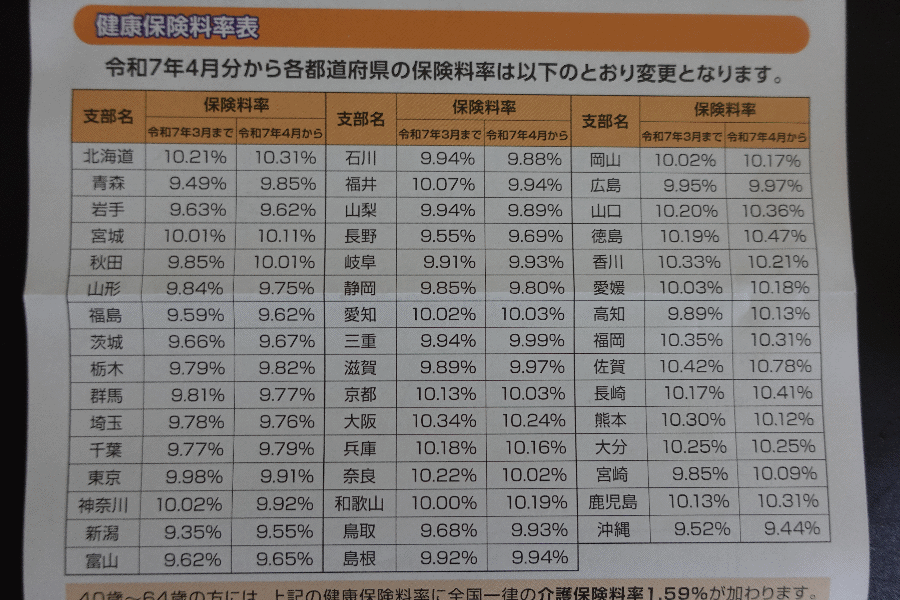
無事にFIREした方も、1年間はなんとか乗り切りましょう。逆にFIREを目指す方は、最初の1年は経費が発生することを覚悟しておきましょう(私は退職前に予習しておきました)。




コメント