■はじめに
私は日本各地に旅行をするが、その交通手段の多くは鉄道である。もちろん鉄道がない地域にもバスやレンタカーを使っていくこともあるが、メインは鉄道旅行である。
よって、鉄道が廃止になってしまうと、めっきり足が遠のいてしまう所も多い。宮崎県の高千穂のような有名観光地であれば廃線後も訪問することがあるが、それほどでもないと、どうしても「鉄道以外の交通手段を調べたり手配したりするのが面倒」になり、疎遠になってしまうのである。
そこで、そういう「ご無沙汰」な場所、つまり「以前は駅があったが今はなく、しばらく訪問していないところ」に行ってみることにした。候補としては、増毛・留萌(留萌本線)、夕張(石勝線夕張支線)、江差(江差線)、岩泉(岩泉線)、十和田市(十和田観光電鉄)、細倉マインパーク前(くりはら田園鉄道)、輪島・蛸島(のと鉄道)、三段峡(可部線)などである。今回は、三段峡に行ってみることにした。上記に例を挙げた中では、一番疎遠なところであり、鉄道を利用した前回の訪問は1998年3月であるから、26年ぶりである(2007年に三段峡には行ったことがあるが、その時はレンタカーで、山陰側からのアクセスであった)。
このシリーズの主な目的は、終着駅再訪と、駅跡や保存車両などの探索である。
■2024.10.13
7時15分の便で広島空港に飛び、同空港からは連絡バスで白市駅へ。駅で可部までの切符を買い(ICでも乗れるが、切符にしてみたかった)、9時27分発の列車で広島に向かった。
広島で可部線に乗り換えるが、35分という微妙な乗り継ぎ時間がある。駅ビルならば駅弁などが売っているが、近距離切符なので途中下車はできない。そこで改札内の蕎麦屋を見ると、広島っぽい辛い麺があったので、それを食べてみることにした。
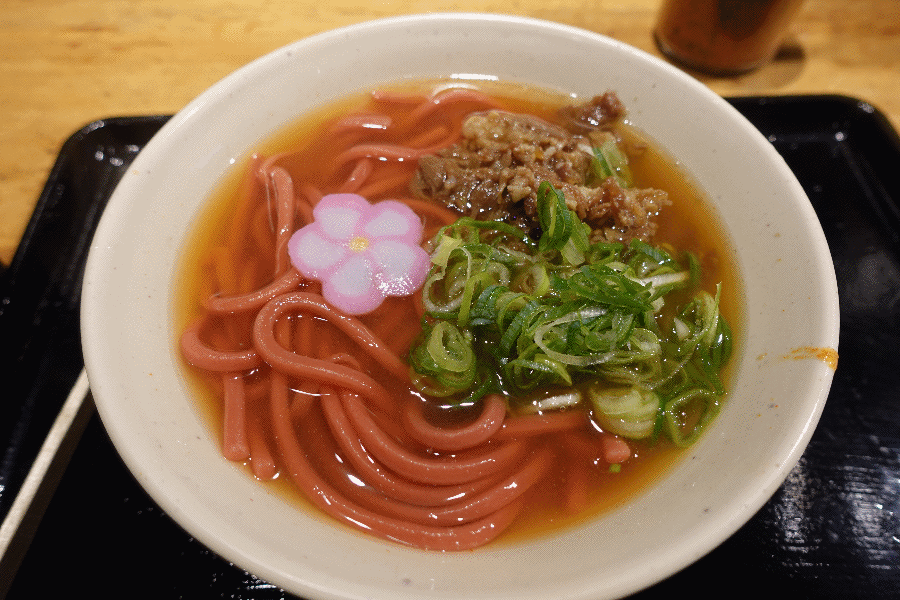
@赤い麺
10時48分発の「あき亀山」行を待つが、なかなか入線してこない。結局、やってきたのは10時46分であった(折り返しとなる列車が少し遅れていた模様)。
急いで席を確保してから、車両の撮影である。可部線は2003年12月に可部から三段峡までが廃止となったが、2017年3月に可部から1.6キロ先まで復活したという、特異な経歴を持つ路線である(廃止となった区間が復活したのは、後にも先にも可部線だけである)。

@あき亀山行
定刻に広島を出発し、ゆっくりと走り続けた。可部到着は11時25分。三段峡行のバスは11時48分発であるため、しばし駅付近を散策である。
しばらくして、三段峡行のバスがやってきた(始発は広島バスセンター)。ここから先は、実質的に可部線廃止区間の代替バスである。
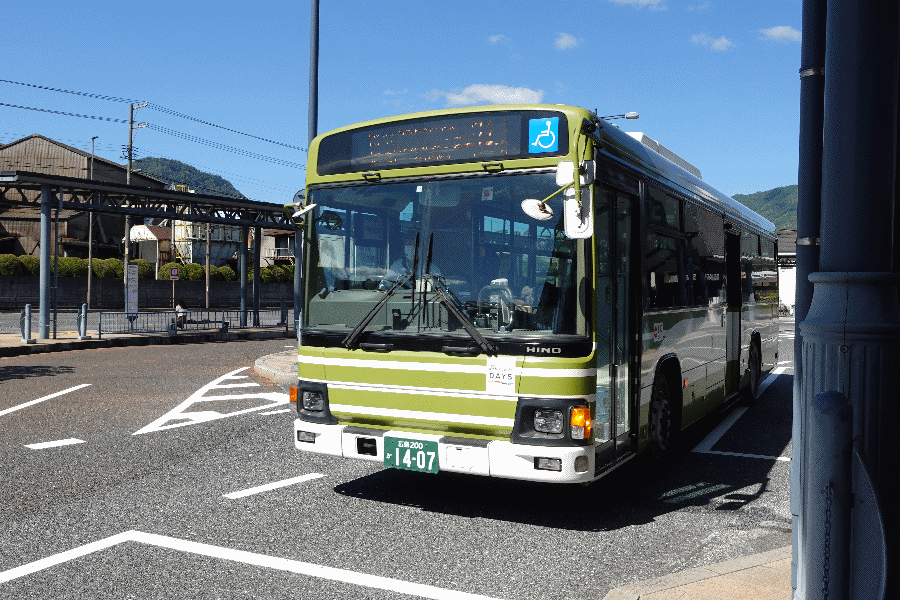
@路線バス
出発後は早速廃線跡に沿って…、とはならず、まずは可部の繁華街へとバスは進んでいく(意外に都会である)。さらにその後も、旧路盤からは離れた国道を進んでいった。
安佐営業所をすぎると廃線跡に沿うようになり、ちらほらと路盤やトンネルや橋梁が見えてくるようになった。
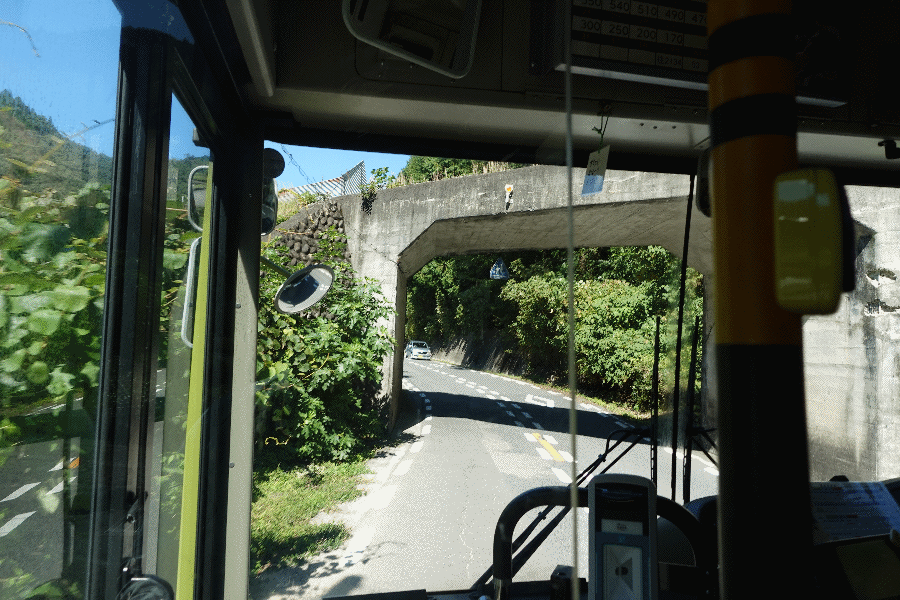
@コンクリート橋をくぐる
国道はひたすら川の北側を走り続けるが、路盤跡は時折長大な鉄橋で対岸に渡ったりこちらに戻ってきたりしている。
折り返し戻ってくる予定の船場(安野駅跡)も過ぎ、しばらくすると津浪駅跡である。ここには売店や食堂もあって降りてみたいと思っていたが、バスの本数が少ないため断念である。

@バス内から撮影(ボケボケ)
街並みが大きくなってきて、定刻から5分遅れた12時56分に加計新町バス停に到着した。
古い家がある道を歩いて、加計駅跡へ。周囲は整備されており、たい焼き屋には長蛇の行列ができている。観光客も多く、意外に賑わっていた。

@ホーム跡
さて、ここでのメインは、車庫に保存されているキハ28系である。折り返しのバスまで時間がないため急いで向かったが、すぐに見つけることができた。しかし、「動態保存」(エンジンが動く状態で保存している)と聞いていたが、「ほんまかいな」と思うくらいボロボロで、路盤も草生していた。
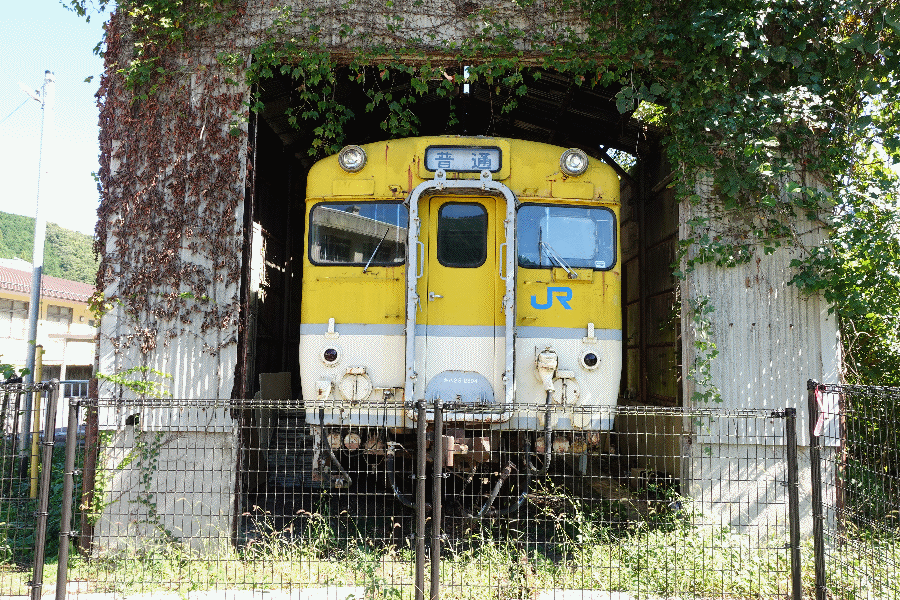
@動く?
急ぎ足で国道に戻り、加計中央バス停から広島バスセンター行のバスに乗り込んだ。先ほどまでの逆回しの景色を見続けて、船場バス停で下車。目の前には安野駅舎がそのまま残っており、「安野花の駅公園」として周囲も整備されている。

@駅舎
駅舎内には、廃線当時の時刻表や料金表が掲示されたままである。1日に8往復運行されていたようで、これは今の路線バス(10往復)とあまり大差ない。
ホームには駅名標も残っているが、それよりも大主張しているのがキハ28系である。
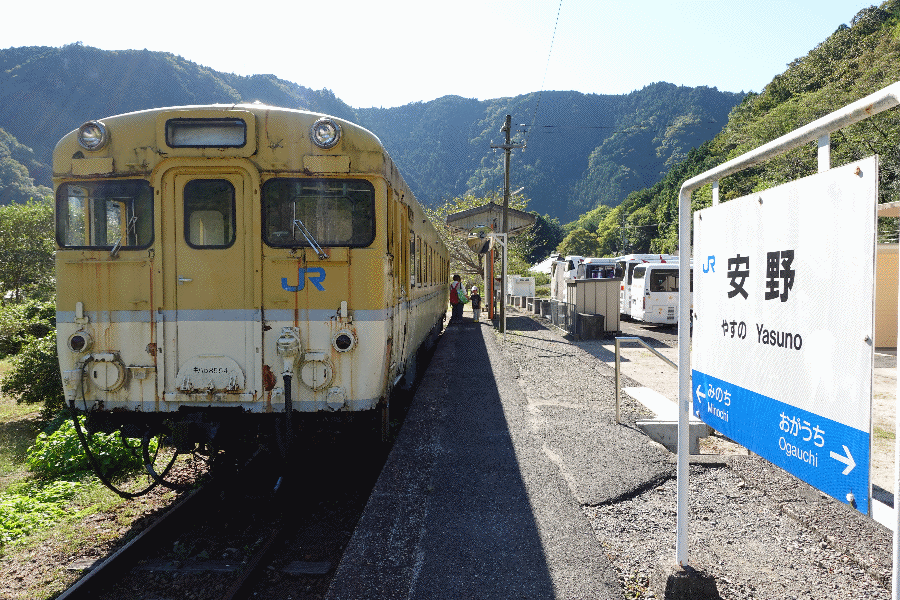
@こちらもボロボロですが
さて、この後は折り返しのバスに乗って三段峡に向かうことになるが、バスが来るまでまだ50分以上もある。ということで、廃線跡に沿ってしばし散策である。
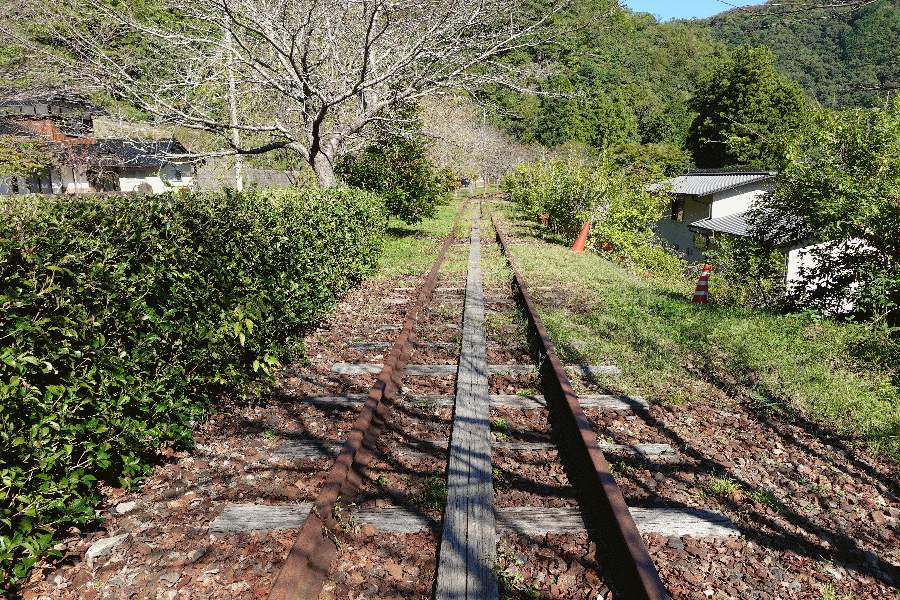
@レールも残っている
しばらく歩き続けると、大きな鉄橋が見えてくる。バス車内からもいくつか撮影していたが、ここで落ち着いて写真撮影である。
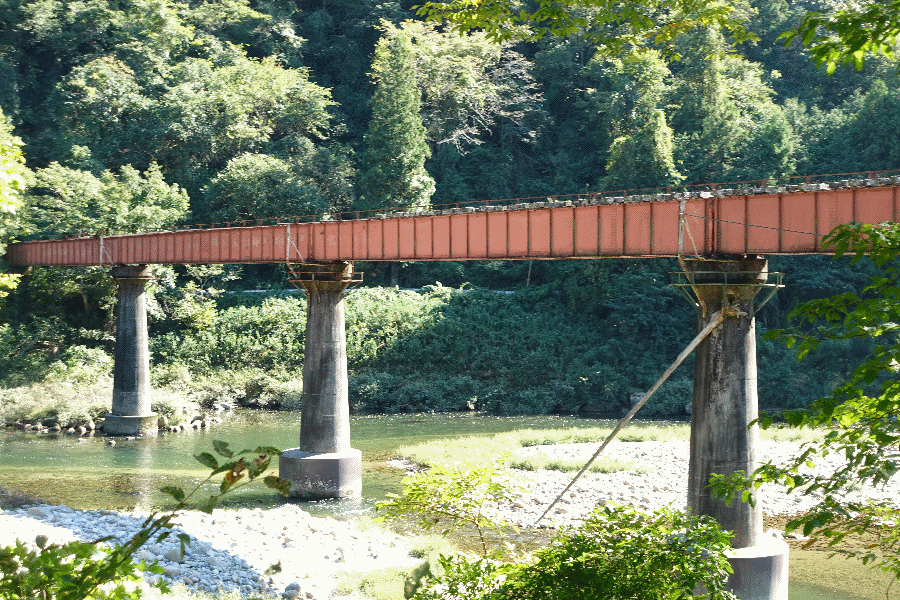
@錆びた鉄橋
10月中旬とは思えない暑さの中(なんと28度)、駅へと歩いて戻っていった。
暇つぶしとして、駅舎内にある写真や新聞のコピー、その他の掲示を読んでいると、ここにあるキハ28系が宇都宮富士重工の製造とあるではないか。私は小学校高学年から宇都宮にいたため、富士重工の引き込み線で完成されたばかりの客車のキハ50系や気動車のキハ183系を見たことがある。
このキハ28系は1964年製ということであり(私が生まれる前)、関係はないが、銘板でもあるかと思って再度車両を見に行った。
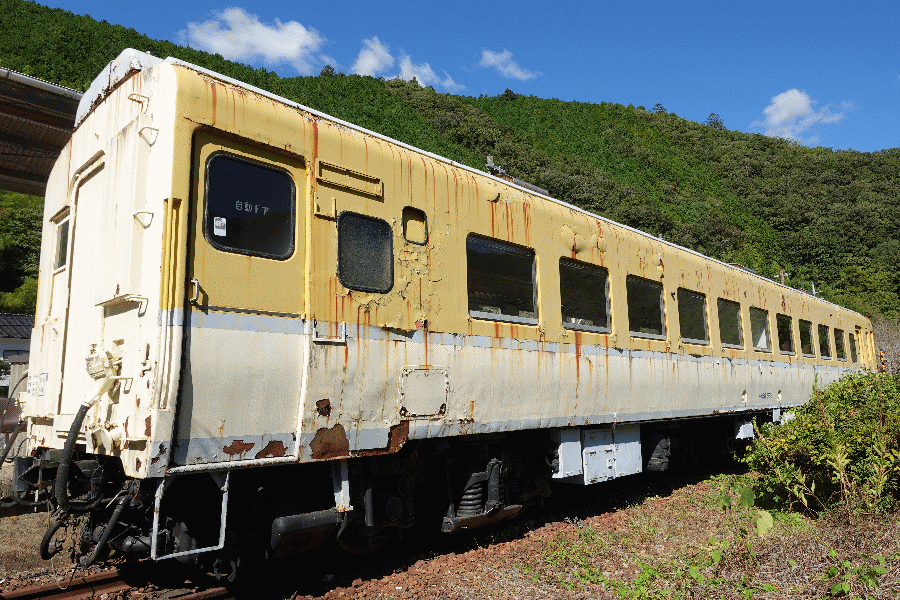
@背後から
残念ながら「宇都宮富士重工」の銘板はなかったが、なんだか感慨一入である。
なお車内は、座席半分、カーペット半分という仕様であった。一度乗ってみたかったと思う。
14時36分発のバス(5分遅れてきた)に乗り、一路三段峡へと向かった。あちらこちらで廃線跡を見ることができたが、三段峡に近づくほど完成年度が新しいため、立派なコンクリート橋を散見することができた。
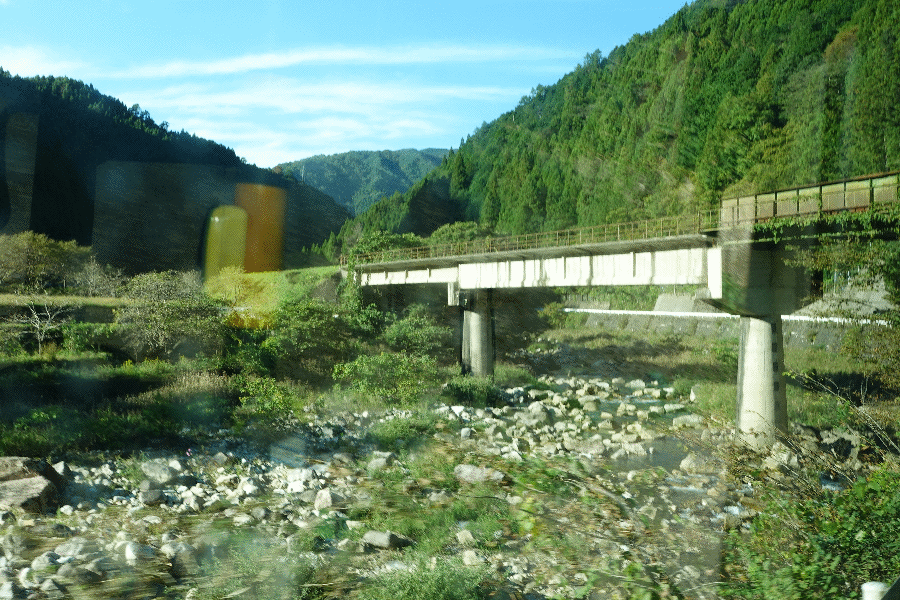
@立派
15時33分頃、三段峡に到着した。駐車場は観光客で大賑わいであったが、駅舎などは当然もうなくなっており、何も残っていない。駅があった名残としては、建物の裏手にレールが少しだけ残っていたくらいである。

@可部線跡
そもそも論であるが、26年前に1回降り立っただけであり、記憶はほとんどない。手掛かりは写真だけであるが、その写真すら2枚しかない。というのも、当時はまだネガフィルムの時代であり(フィルム購入・現像にかなりの経費が掛かるため)、「ここぞ」というタイミングでしかシャッターは押せなかったのである。
レールの末端部分は、上記写真とは少し違う場所のようである。しかし、表紙写真を見ると、反対側の周囲の山の稜線は変わらないままである。

@レールの最後(1998年)
折り返しのバスまで40分くらいしかないが、せっかく三段峡に来ているので少しだけ渓谷部分を歩くことにした。三段峡のメインとなる部分(船に乗ったりする部分)は16年前のレンタカー旅行で経験済みであるから、今日は「つまみ食い」で充分である。
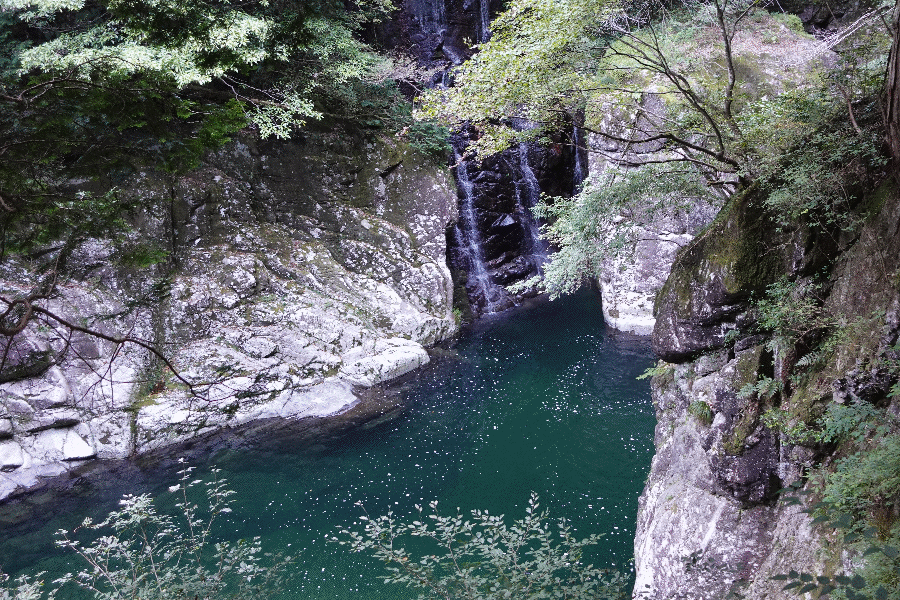
@三段峡
散策路には古い看板が残されてあり、「おみやげは駅前峡内入口にてお買もとめ下さい」などとあるのも一興である。
バス停付近に戻り、路線バスとJRを乗り継いでひたすら広島へ。広島駅付近に安ホテルが見付けられなかったため、今日は海田市駅付近のホテルである。
■2024.10.14
ホテルをチェックアウトしてやって来たのは、隣駅の向洋に近いマツダ本社である。というのも、マツダのミュージアムは平日だけ見学可能で土日は訪問できないのだが、祝日に関しては予約可能な日があるため、事前予約してあるのである。
9時15分になり、専用バスで工場内を走ってミュージアムに向かう。色々と気になるものは多いが、工場内は撮影禁止である。
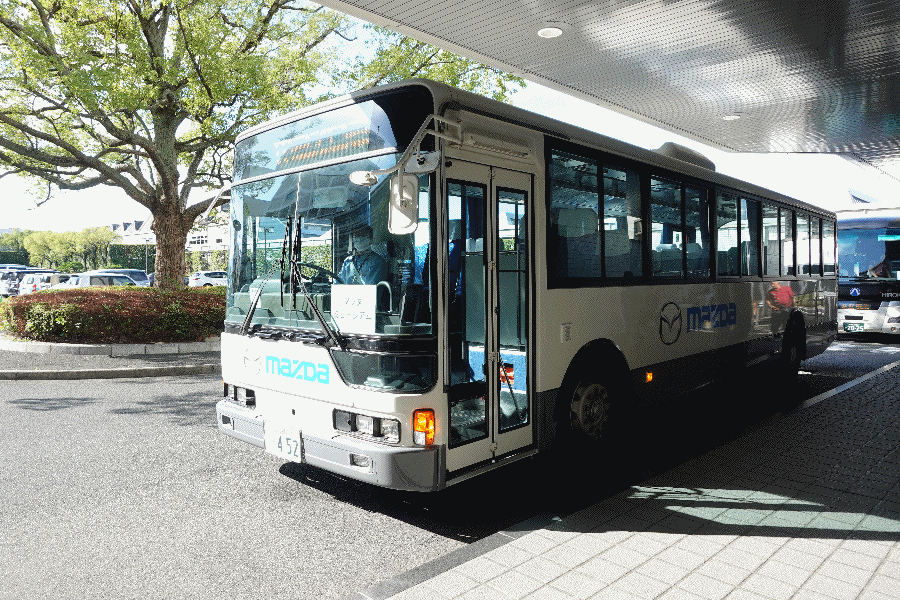
@バス写真で代替
工場内にある大きな橋(当然マツダ専用)を渡り、10分ほどでミュージアムに到着した。専用の若い女性ガイドの案内に従って(今日は館長も参加して追加の説明をしていた)、古い歴史から様々な車両、色々な技術や将来的な計画について説明がなされていった。私くらいの年代(1970年生まれ)であると、やはり気になるのはこの辺りであろうか。
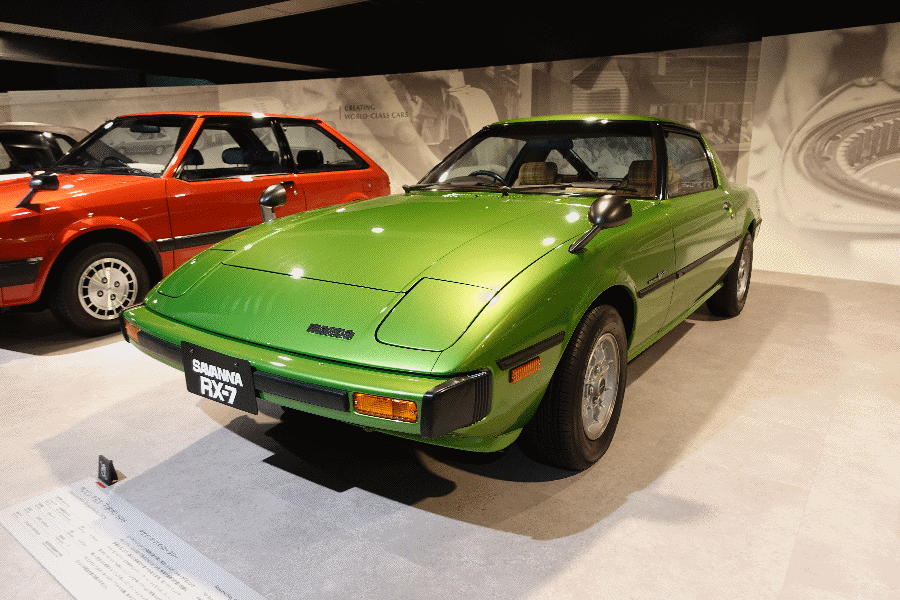
@RX-7
市販車以外でやはり注目すべきは、ル・マン24時間耐久レースで日本車として初めて優勝した787Bであろう。ここに置いてあるのは実際に走行した車両ということであったので、ということはフランスのル・マンにある自動車博物館に展示されていた787Bは、実走した車両ではないということであろうか。
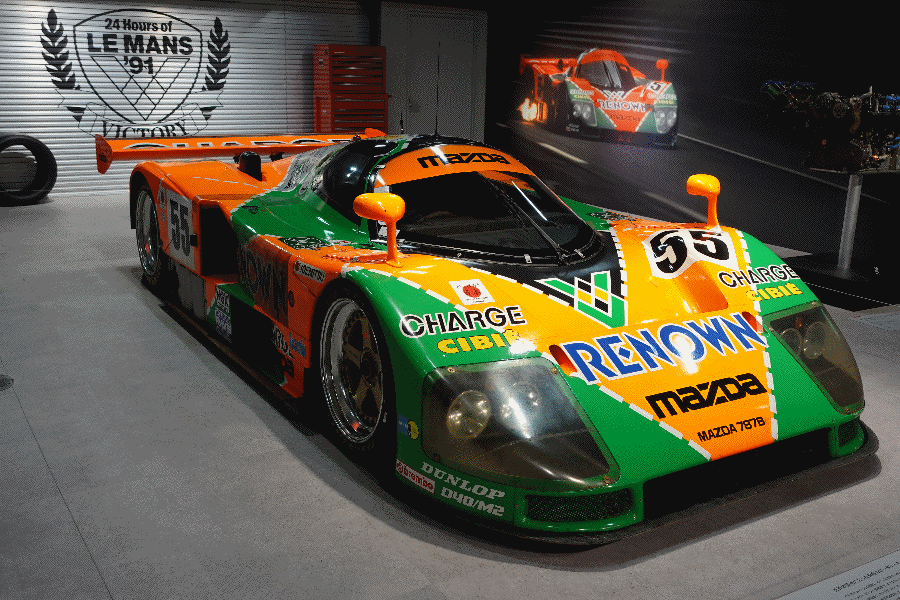
@787B
工場のレーン見学もでき、無料にしてはかなり充実した内容であった。
11時15分頃に見学は終了。JR向洋駅に行き、やってきた列車に乗って隣駅である天神川で下車した。というのも、ここから歩ける場所にあるイオンモールに行くためである。
モールに行くと言っても、買い物のためではない。この敷地にはSLが展示されており、このSLは、実は昔の三段峡駅近くに展示されていたものなのである。三段峡駅跡に置いていた方が「ここに駅があった証」になるのになぁ、と思う気もするが。
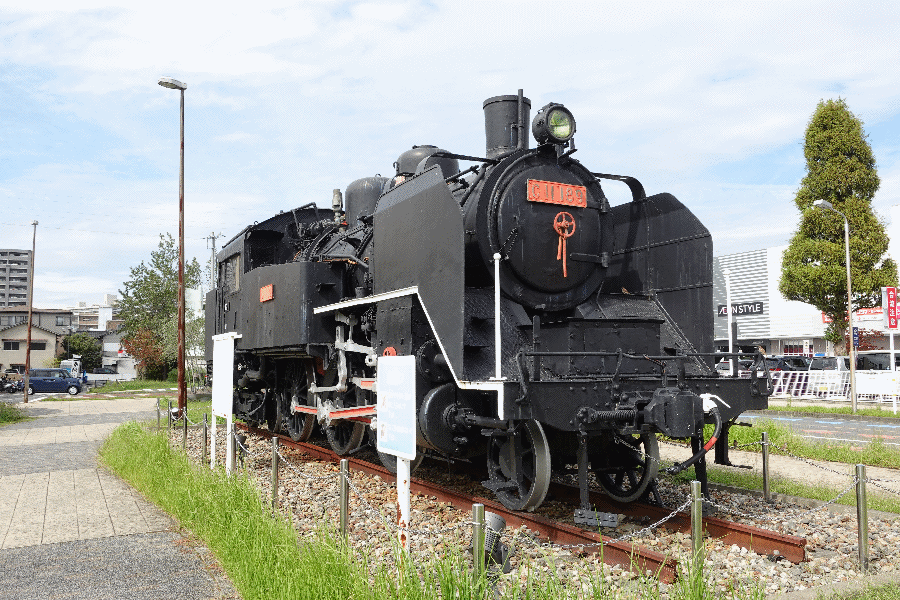
@SL
可部線に関する最後の残像物を確認し、これで今回の旅の目的は終了である。
この後は家に帰らず、広島で所用を済ませることにしている(その移動を利用した旅であった)。この日は広電を何回か利用したが、稀に古い車両(京都市電)がやってくると、ラッキーな気分になる。

@当たり車両




コメント