■はじめに
鉄道が廃線となってご無沙汰となっている終着駅へ行くこのシリーズであるが、今回は北海道の夕張駅である。
石勝線の夕張支線については、2019年4月に「攻めの廃線」などという訳の分からない当時の市長(現道知事)による施策で廃線となったが、その後の公共交通機関の衰退は甚だしく、効率的な廃線であったとは全く言えない(元より乗客は少なかったため、遅かれ早かれ廃止になっていたであろうが、事を急ぐ必要は全くなかった)。
代替の路線バスは設定されたものの、JRの新夕張駅での接続は恐ろしく悪く、観光が全く意識されていない。更に、札幌から夕張に向かう路線バスは2024年9月に廃止されてしまい、また、市内にあった複数のホテルもコロナ禍の2020年に営業を終えてしまい、ふらっと「夕張に旅行に行こう」と思っても、アクセスは悪い・宿泊できないため、手軽に観光することもできなくなってしまっている。
気軽に宿泊できないのが一番調整し難いところであるが、廃校を再利用した宿泊施設が出来たため(スキー客用であるが、夏は少し安く泊まれる)、そこを確保した。1人利用で9,600円であり、冬季でなくてもそれなりに高いが、クーポン(2,500円)とポイント(1,500円)を適用させて、5,600円まで下げてみた。
また、おまけとして、1987年に廃線となった幌内線(終着駅は幾春別)の跡も辿って来ることにした。
■2025.10.6
空港までや現地での移動は個別に切符を買う予定であったが、計算してみると、「秋の乗り放題パス」を使うとほんの少しだけ(150円くらい)安くなることが判明した。よって、それを事前に入手してある(都度切符を買う煩わしさも無くなる)。
家を出て、5時07分発の始発列車に乗って移動した。
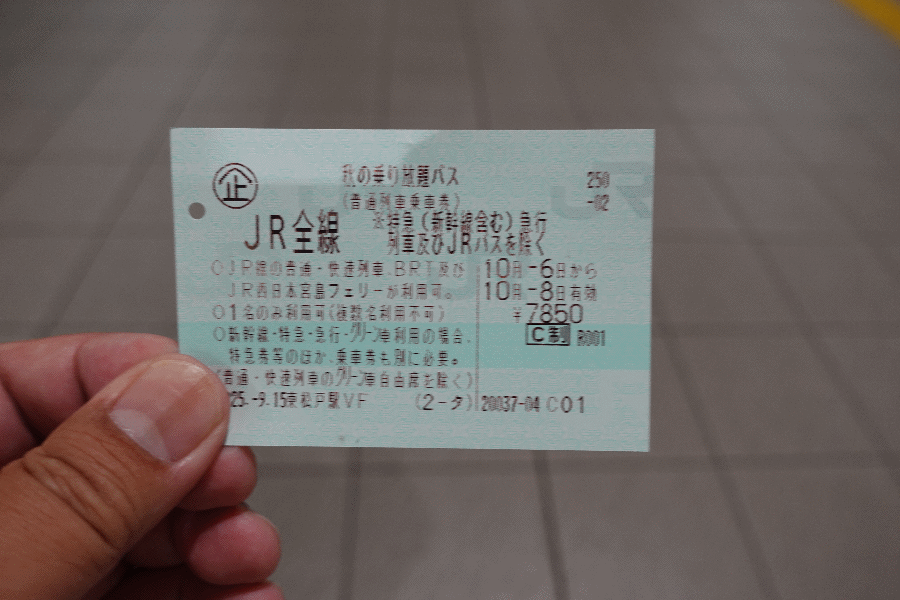
@初めて使うかも
いつもならば羽田空港へ向かうが、吝嗇癖が治らず、今日は成田空港へ向かってLCCで飛ぶこととなる。
JRを何度か乗り換えて成田空港に向かい、久々に第3ターミナルにやって来た。
手続きをして、7時50分発の便で新千歳へ向かった。
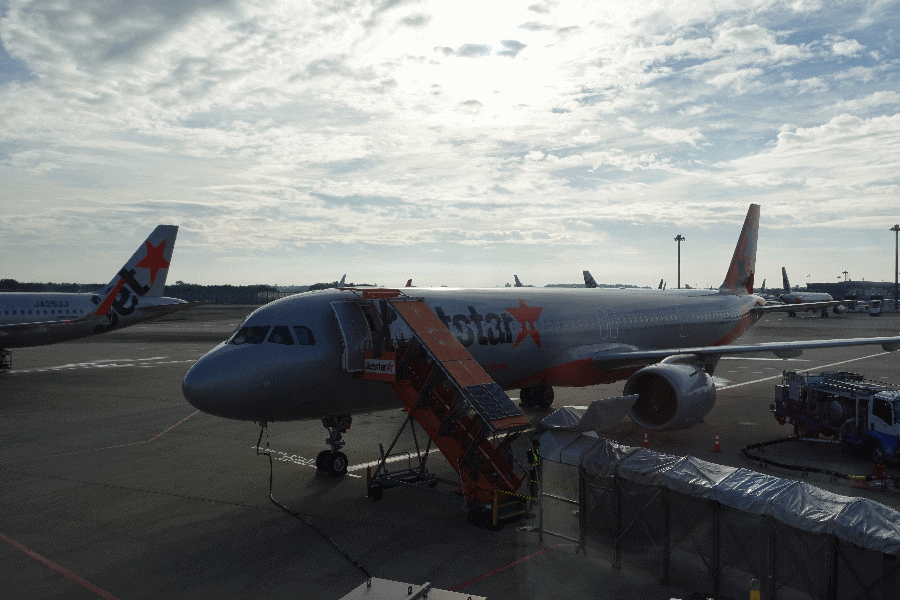
@LCC
9時半過ぎに新千歳に到着し、中途半端な時間はカードラウンジに滞在して調整し、11時頃にJRの駅に向かった。札幌行の快速列車に乗り、千歳で下車した。
通常の切符の場合、新千歳空港から新夕張に向かう場合は南千歳で乗り換える必要があるが、乗り放題の切符にしたため、このような乗り継ぎが可能となる(始発駅から乗ることができる)。
ということで、次に乗るのは11時35分発の新夕張行である。

@1両編成
他の列車の遅れが影響して2分ほど遅発し、南千歳まで戻り、そこから分岐して石勝線に入って行った。
終着の新夕張には、定刻から4分遅れた12時35分に到着した。本来の到着予定は12時31分であるが、バスはその直前の12時12分に出発してしまっており、次のバスは2時間半後という、「各駅停車では旅行ができない」乗り継ぎである。

@新夕張駅
元よりそれは承知済みであるため、今日は歩いて廃線跡を巡ることにしている。
駅から歩き出して石勝線の高架を潜って行くと、夕張支線の廃線跡(路盤など)が左に見えて来る。跨線橋を過ぎると、それは右手になっていった。

@廃線跡あれこれ
新夕張駅から45分ほど歩いて、やっと沼ノ沢駅跡に辿り着いた。しかし、駅舎はすべて解体されてしまっており、跡形もない。というのも、JR北海道では、雪による建物の倒壊などを防ぐために、廃線となった駅だけに限らず(路線が残っていて駅だけ廃止となった場合も含めて)駅舎の解体を進めているのである。
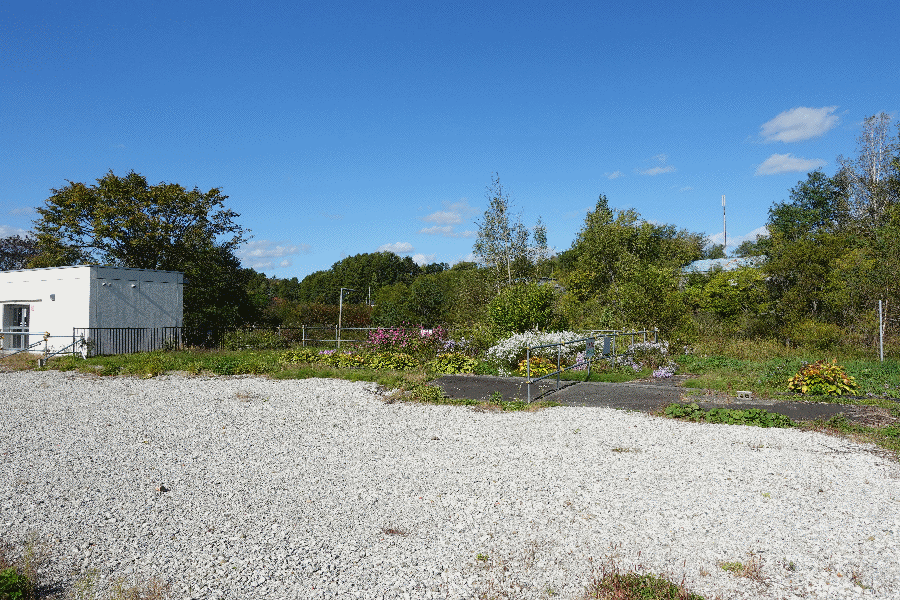
@何も無し
続いて目指す廃駅は、南清水沢である。スマホに計らせると55分と表示されたが、長閑な田舎道(暑くも寒くもない)であるため、疲労感は無い。
橋梁などの廃線跡が見えて来るたびに、それを写真に収めた。

@廃線跡あれこれPart2
ひたすら歩き続け、やっと南清水沢駅跡に辿り着いた。こちらは、無事に駅舎が残っている。というのも、駅跡が蕎麦屋として利用されているからである。

@ある意味「駅そば」
宿泊先付近にはコンビニしかないため、道路の向かいにあるスーパーで夜用食材を買い込み、そして次の駅に向かった。
歩いて20分ほどで到着したのが、清水沢駅跡である。こちらは、完全に解体されて整地されてしまっている。更地の写真を撮っても仕様がないため、高架橋に上がってホーム跡などを撮ってみた。
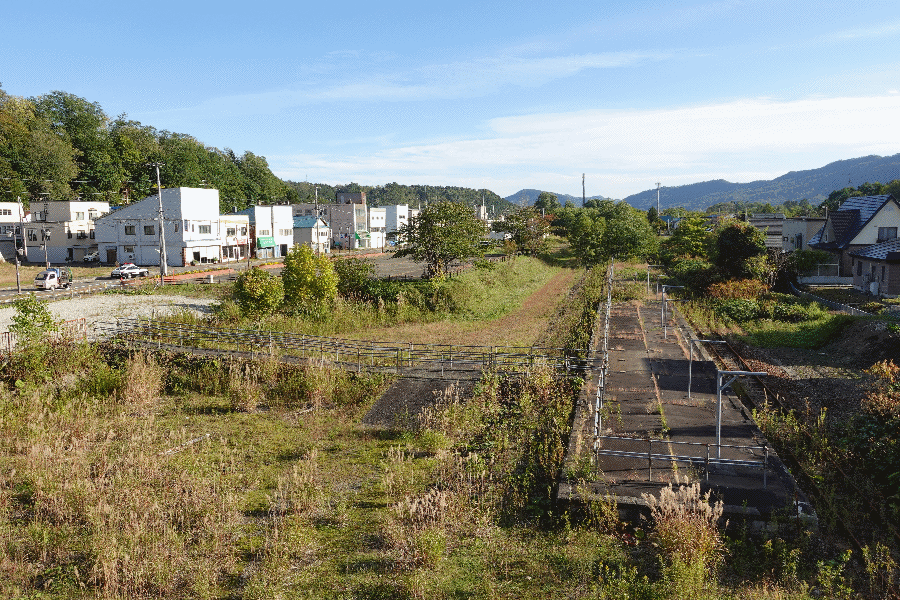
@清水沢駅跡
駅前にはいくつかの店舗が並んでいるが、すべてシャッターは閉まっている。通りを歩く人も、誰もいない。流れて来る町内向けの音楽だけが、寂しく響いている。
次の駅は鹿ノ谷であるが、ちょうどバスが来るタイミングであるため、それに乗ることにしている。
駅にほど近い清水沢3丁目バス停で待ち、15時12分発のバスに乗り込んだ。

@路線バス
車内には、意外にも多くの乗客がいた(20人くらい)。もちろん、すべて交通弱者(生徒や学生と、高齢者)である。
鹿ノ谷郵便局バス停で降りて、脇道に入って行くと、見えて来るのが鹿ノ谷駅である。ここは駅舎が残っているが、それは保存会があるからである。
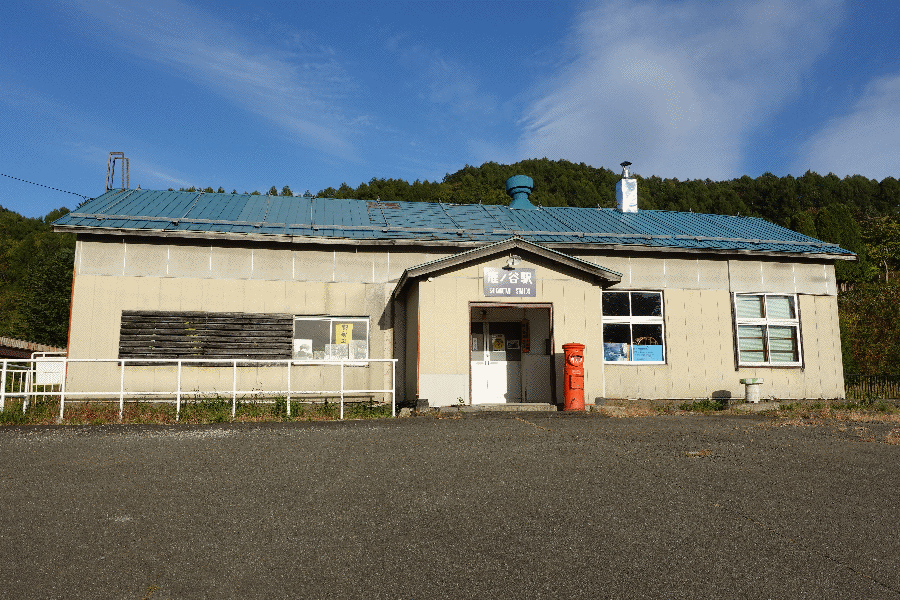
@立派な駅舎
ホームも残っていたため、そこに入ってみた(表紙写真)。この駅は以前に訪問したことがあるため(まだ夕張支線が現役であった頃)、懐かしい限りである。
せっかくであるから、その時の様子(2019年2月)を1葉だけ紹介しておきたい。
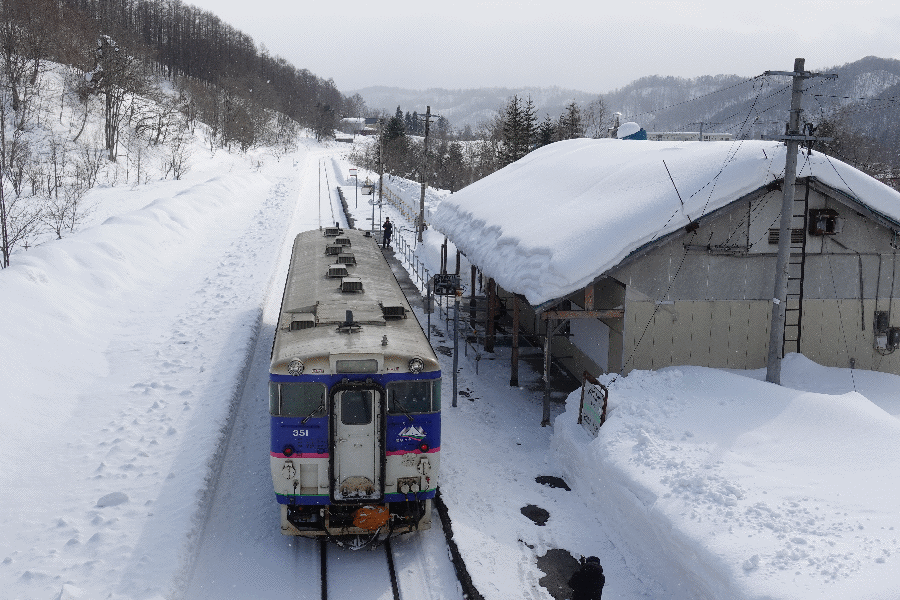
@冬の鹿ノ谷駅
駅の状況を確認し、これから宿泊先に向かうが、その前に第五志幌加別橋梁に寄って行くことにしている。
この橋梁であるが、北海道炭礦鉄道が複線であった時代のものである。奥にある橋梁は夕張支線としても使用されていたが、手前の橋梁はほんの13年しか使用されなかったという複線時代の名残である。
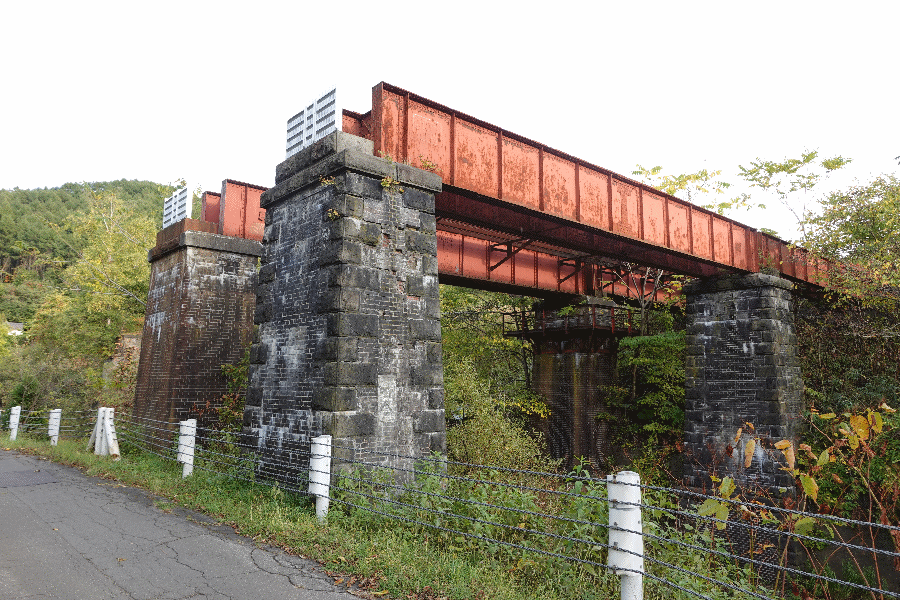
@旧い橋梁
日が傾きつつある中を歩き、今日の宿泊先に辿り着いた。見るからに学校であるが、ここは夕張北高(生徒減少により1994年に閉校)の建物を再利用したものである。
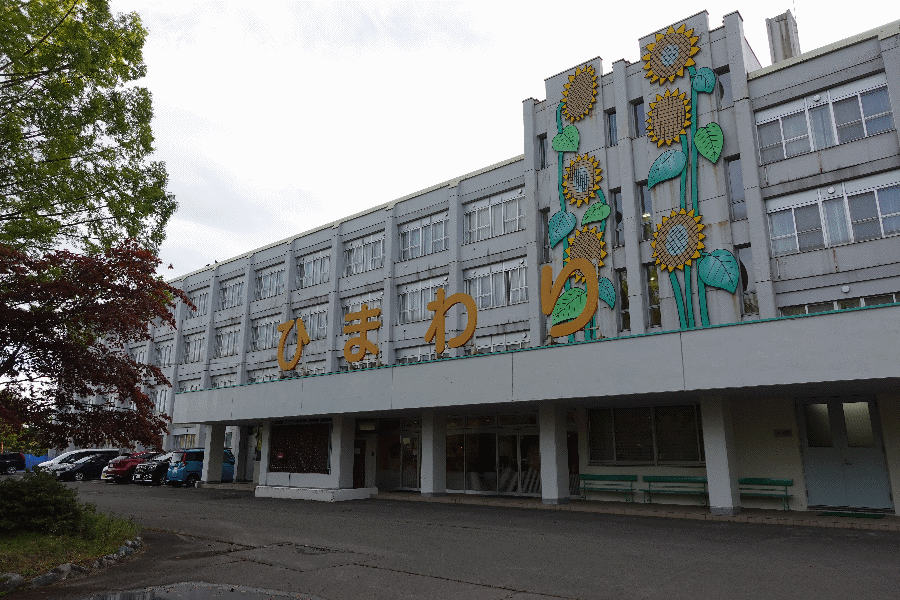
@元は学校
支払いはネットで済ませているため、手続きだけをして部屋に向かった。部屋は教室を半分にしたくらいの広さであり、1人では寂し過ぎるくらい広い(8人まで泊まれるようである)。なお、布団は自分で敷かなければならない。

@広すぎ
荷物を部屋に置いてから、アルコールを買うためにコンビニに向かった。
通りを歩いて行きしばらくすると右手に大きなリゾートホテル(休業中)があるが、その手前にある三角屋根の可愛い建物が、夕張駅であったものである(現在は、カフェとして営業中)。
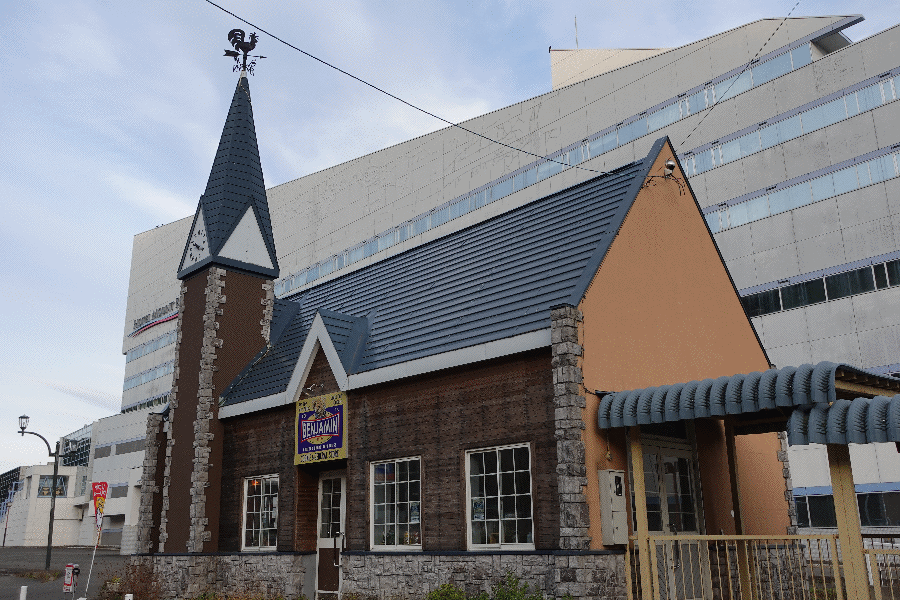
@夕張駅
コンビニに行って酒などを買い、宿泊施設に向かって戻り始めた。それにしても、通りは出歩く人も皆無でうら寂しく、なんだか物悲しい気持ちになってしまった。
部屋に戻った時点でまだ17時くらいであり、まずは建物内の探索である。イメージとして机などが残されている場所や、北高関連の展示スペース、各種賞状、エントランスなどである。

@あれこれ探索
その後は、大浴場に浸かってから、スーパーやコンビニで買い揃えた食材で一献し、就寝。
■2025.10.7
7時半過ぎに宿を出て、夕張駅跡の前を過ぎて更に歩き、夕張の住宅街までやって来た。ここまで来て、やっと「あの家には人が住んでいるな」という雰囲気が出てきたが、それも疎らである。
「本町キネマ街道」と名付けられていて各所に映画の看板があるが、いずれも色褪せているし、それを見に来ている観光客も皆無である。
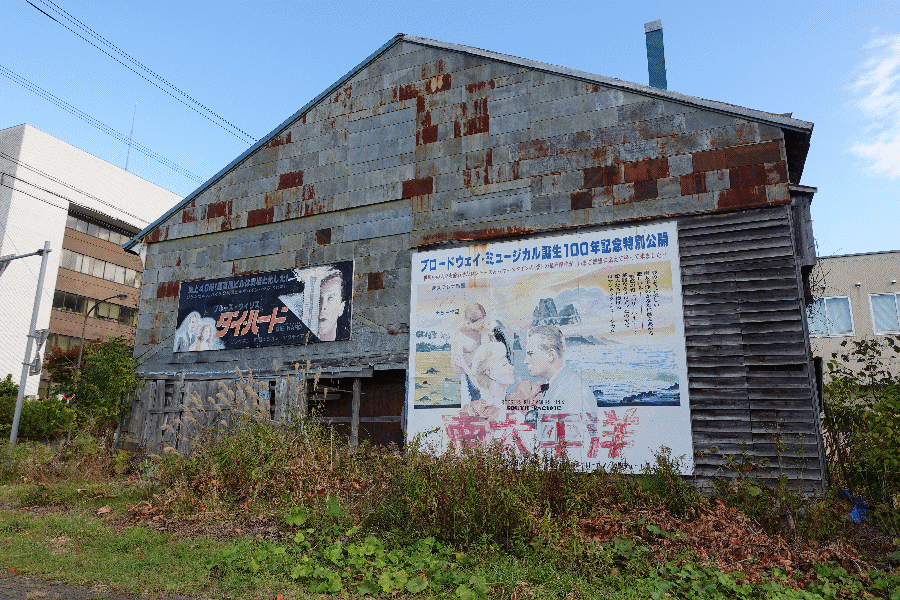
@看板の例
寂しい街中を過ぎ、以前泊まったことがあるホテル(廃業)の前を過ぎ、更に歩き続けて、「石炭博物館」までやって来た。以前に入ったことがあるので今日は訪問しないが(そもそも火曜日は休館日であるし、まだ朝の時間帯である)、だだっ広い駐車場のアスファルトもかなり古くなっており、場末感が漂っている。
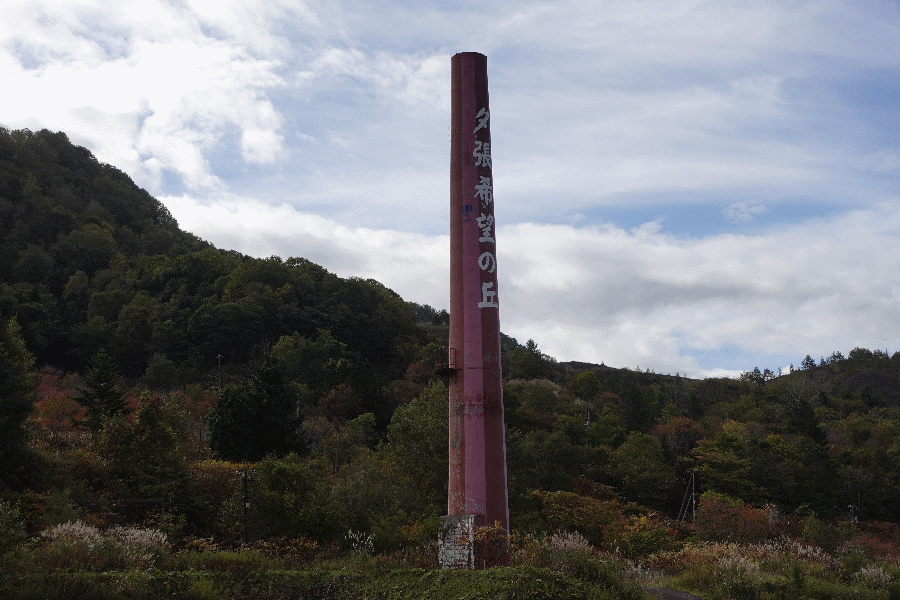
@煙突
近くにあった夕張神社を参ってから元来た道を戻り、夕張駅跡まで戻って来た。駅舎(カフェ)の裏手にはホームやレールが残ったままであるが、当然列車は来ないため、草生した状態になっている。

@現状
(前回訪問時に同じ角度から撮った動画は、以下である)
すぐ近くにあるレースイ前バス停からバスに乗る予定であったが、まだ時間があったため、鹿ノ谷まで歩いてからバスに乗り、新夕張まで移動してきた。バスの車内では観光案内もあり、最後には「またぜひ夕張にお越しください」などとあったが、その時点で車内にいた乗客は私を含めてもたった2人だけであるから、寂しい限りである。
新夕張駅には10時18分に到着したが、千歳行のJRの出発まで3時間近くもある(各駅停車は、早朝と昼と夜の3本しかない)。「特急に乗れ」と言われればそれまでだが、今回の切符では乗れないため、近くの道の駅に行ったりして時間潰しである。
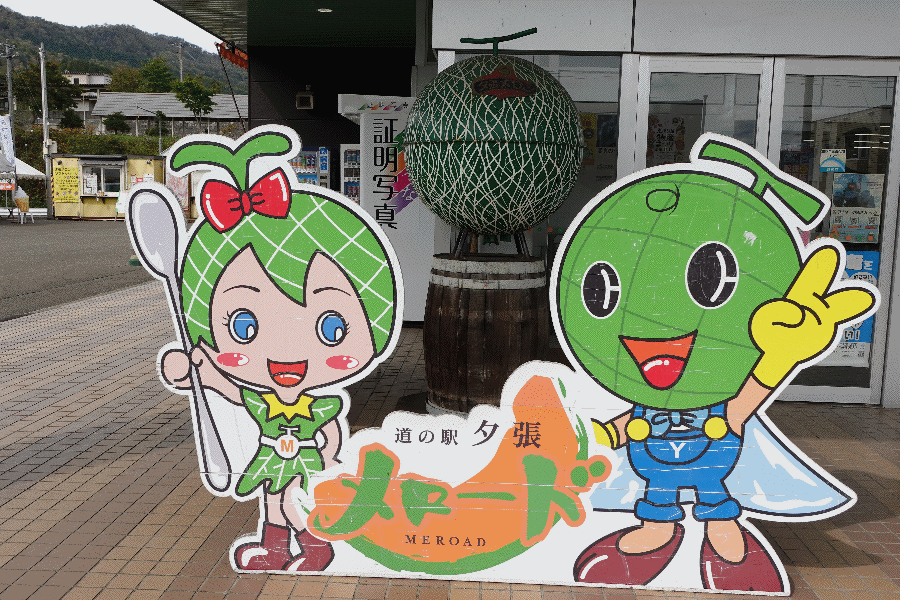
@道の駅
以前は鉄道コーナーもあった道の駅であるが、それらはすべて撤去されてしまっていた。駅に戻り、余った時間はこの旅行記の作成である(幸い、机と椅子があった)。
13時07分まで待つのは面白くないため、11時54分発の帯広行の特急に乗ることにした。というのも、石勝線の新夕張から新得までは特急しか走っていないため、特例で特急券なしで特急に乗車できるのである。
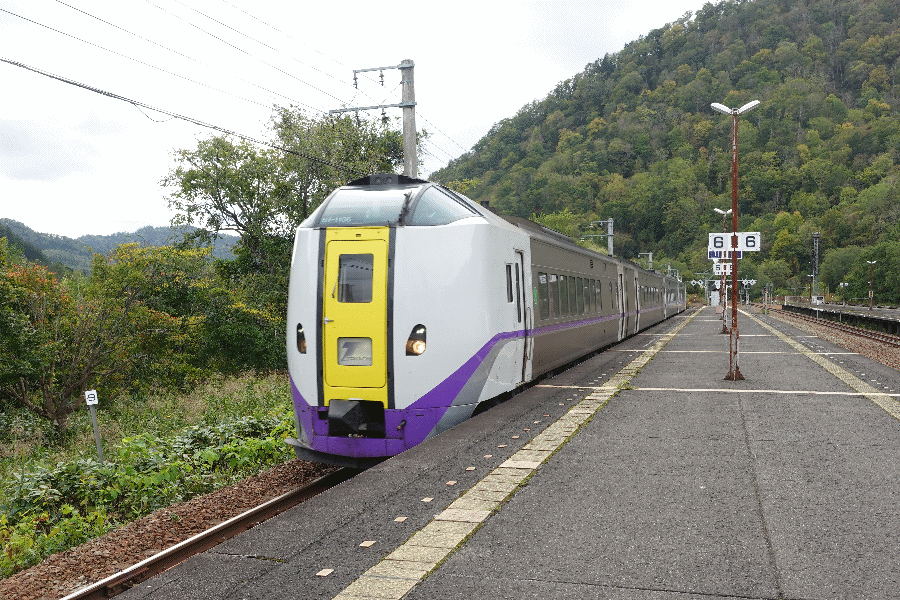
@気分転換に特急に乗る
その特急に乗り、次の駅である占冠(しむかっぷ)で下車した。すぐ近くに無料の郷土資料室があったので、それを見て時間潰しである(鉄道ネタは皆無)。
12時36分発の特急で新夕張に戻り、新夕張からは13時15分発の各駅停車で千歳まで移動して、快速に乗り換えて北広島にやってきた。
そこから向かったのは、エスコンフィールドである。

@始めて来た
試合がない日であれば外野に入ることができるのであるが、今日はクライマックスシリーズに向けた有料の紅白戦をやっているということで、残念ながら外から眺めるだけである。
敷地にある公園を歩いてから、駅へと戻った。そもそも論であるが、北広島に来た理由は、今日のホテルがこの駅前にあるからである(インバウンドの影響で、札幌のホテルは高くて泊まれない)。

@ホテルフロント付近
スーパーに行って北海道名物鳥の半身揚げを買い、それで一献してから就寝。
■2025.10.8
今日は、1987年7月に廃止となった幌内線の跡を巡ることにしている。ホテルをチェックアウトしてJRを乗り継いで、岩見沢までやって来た。
続いて乗るのが、8時30分発の幾春別町行のバスである。
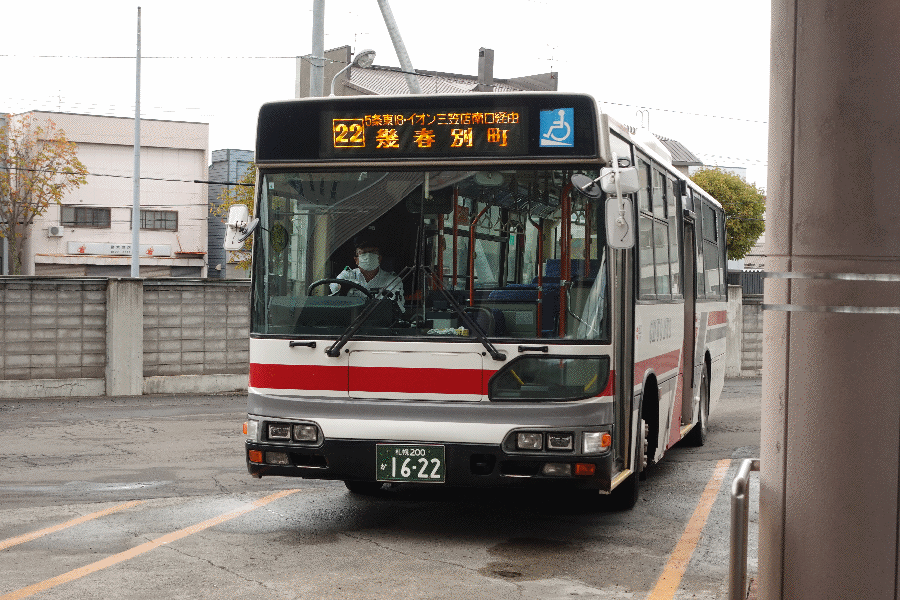
@バスで向かう
定刻に出発し、9時06分に到着した三笠市民会館バス停で降りて、最初に向かったのがクロフォード公園である。公園の名は北海道に米国の鉄道技術を伝えたジョセフ・ユリー・クロフォード氏に由来しているものであり、ここは幌内線の三笠駅があった場所となっている。
敷地にはディーゼル機関車や特急の車両が係留されているが、特に特急車両は塗装の剥げが激しいようである。クラウドファンディングなどしてはどうかと思う。
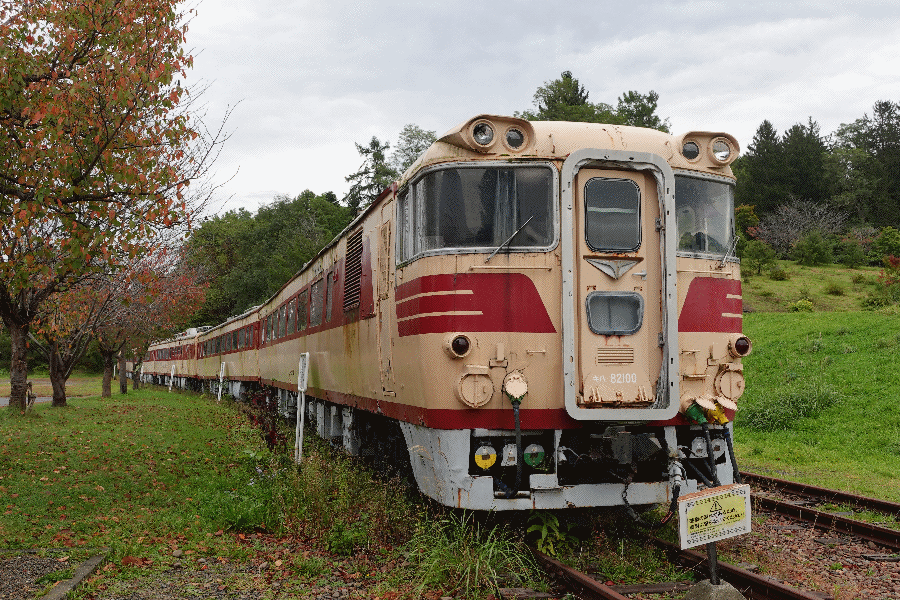
@だいぶ剥げてきた
ここから南方に向かうと三笠鉄道記念館という立派な鉄道関係施設があるが、以前に訪問済みであるため、今日は幾春別方面に向かって歩くことにしている。
今日もまたひたすら歩き続けること約55分、唐松駅跡に辿り着いた。ここはホームだけでなく、駅名標や駅舎などもすべて保存されている。
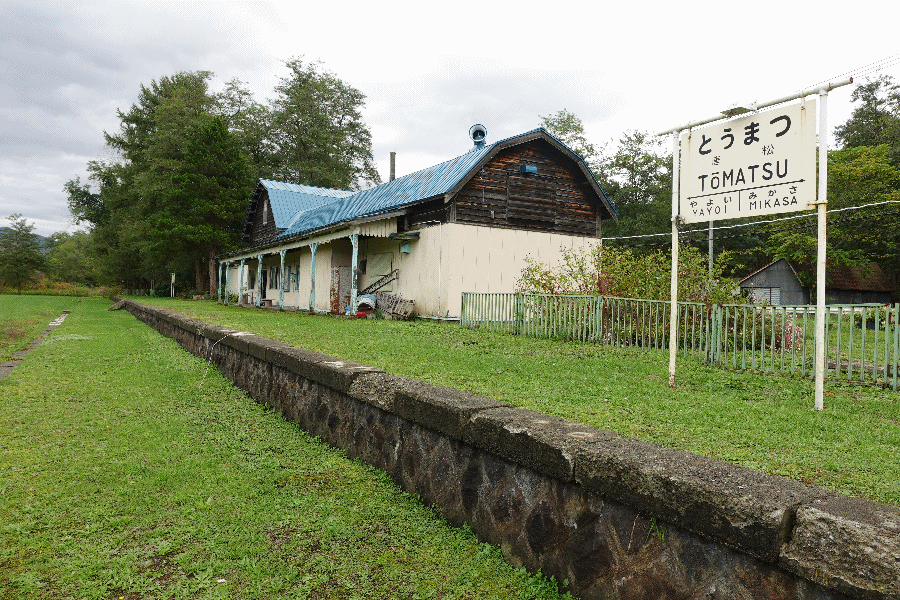
@唐松駅
しかも駅舎内も奇麗に整理されていて、多種多様の写真が展示されていて、昔の案内掲示などもそのままになっている。廃駅などは、人の手が入らないとすぐにガタついてくるが(よってJRも解体を進めているが)、定期的に整備されていると(必要な補修が行われるため)、きちんと保存ができるようである。
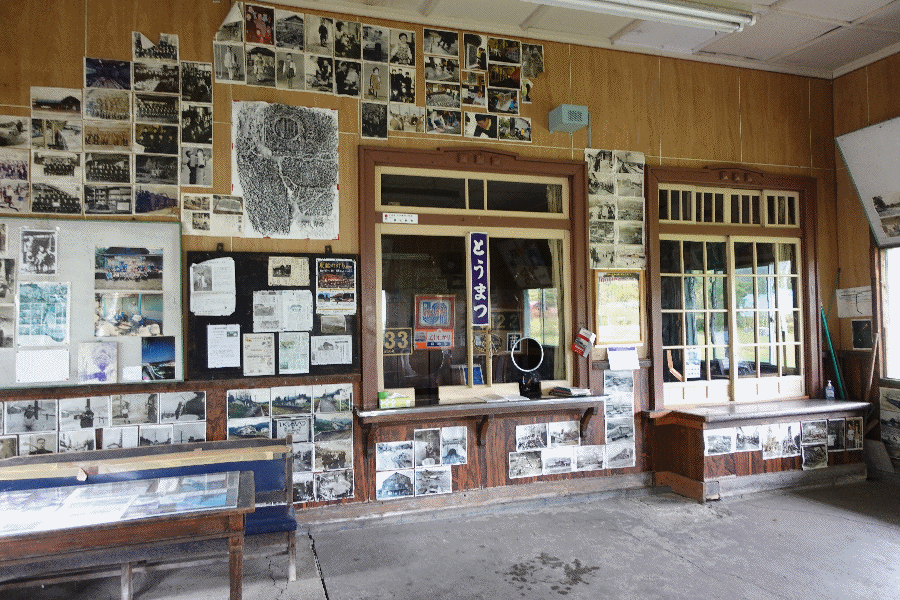
@駅舎内
駅の見学を終えてからは再度歩き始め、約30分ほどすると、次の駅は弥生である。ここの駅舎はとっくの前に解体されているが、駅跡を訪問したことがなかったため、訪れることにした。
待ち構えていたのは、石碑だけであった。
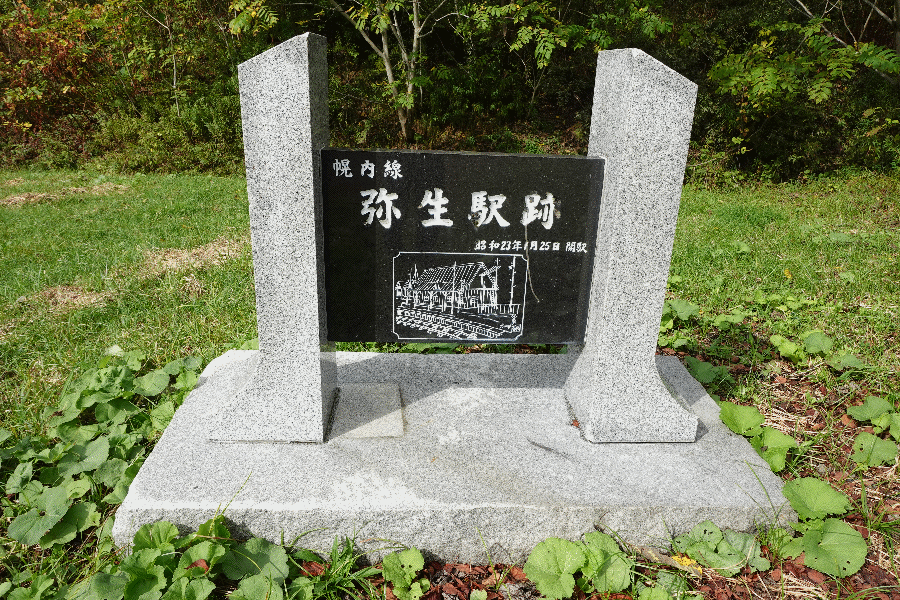
@弥生駅跡
その後も更に20分ほど歩くと、幌内線の終着駅であった幾春別である。しかし、ここも弥生駅と同様に石碑しか残っていない。
石碑の写真が2枚続いたのでは寂しいので、今から39年前に訪問した際の幾春別駅の様子を、1葉紹介しておきたい。
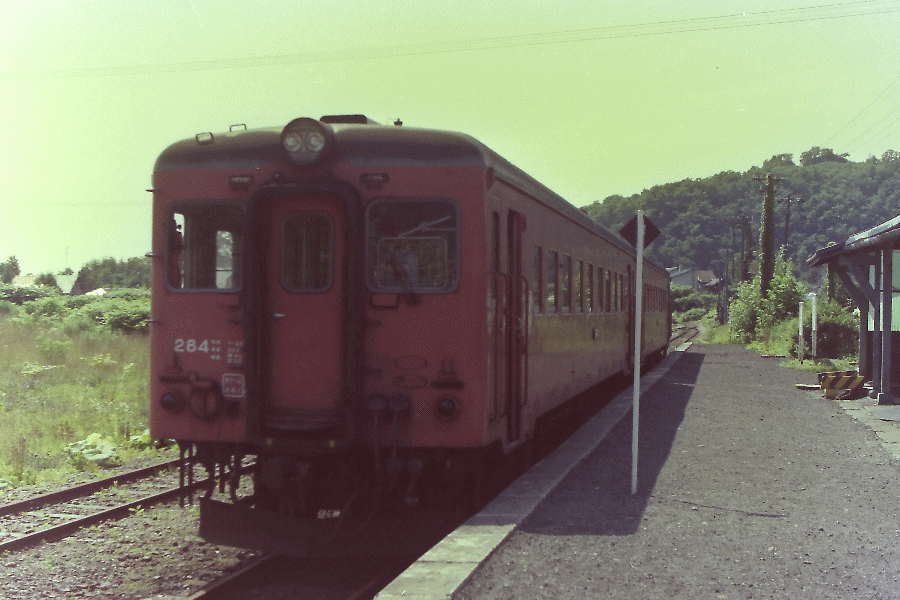
@当時の様子
これで、幌内線跡の探索は終了である。これから11時30分発のバスに乗って岩見沢に向かい、JRを乗り継いで新千歳空港まで移動して、15時35分発のLCCで帰路に就くだけである。
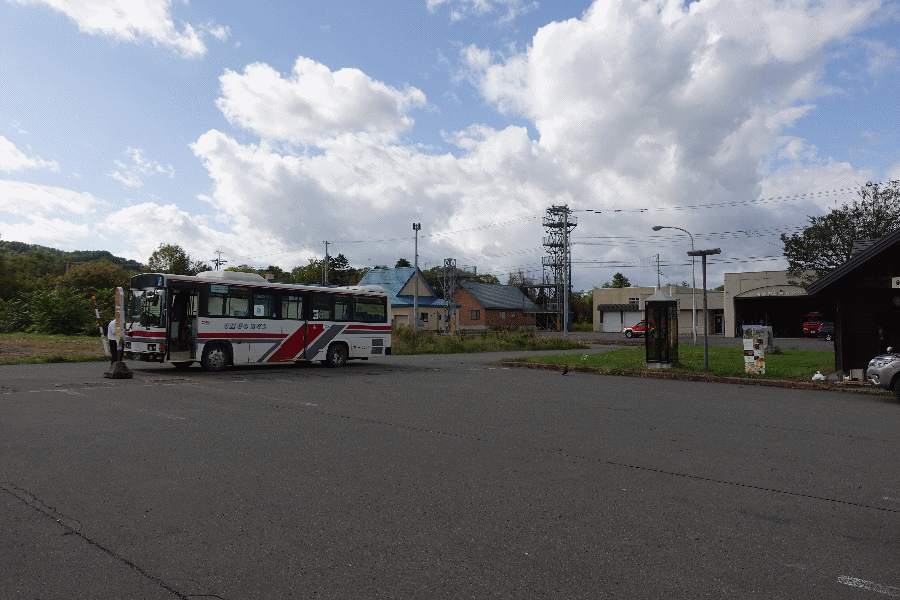
@幾春別駅跡はバスの発着所になった
【過去のシリーズ】
駅のない終着駅へ Part1(三段峡駅)
駅のない終着駅へ Part2(加津佐駅)
駅のない終着駅へ Part3(おまけで「惜別・留萌本線」)(留萌駅・増毛駅)
駅のない終着駅へ Part4(輪島駅)
駅のない終着駅へ Part5(細倉マインパーク前駅・十和田市駅)
駅のない終着駅へ Part6(岩泉駅)

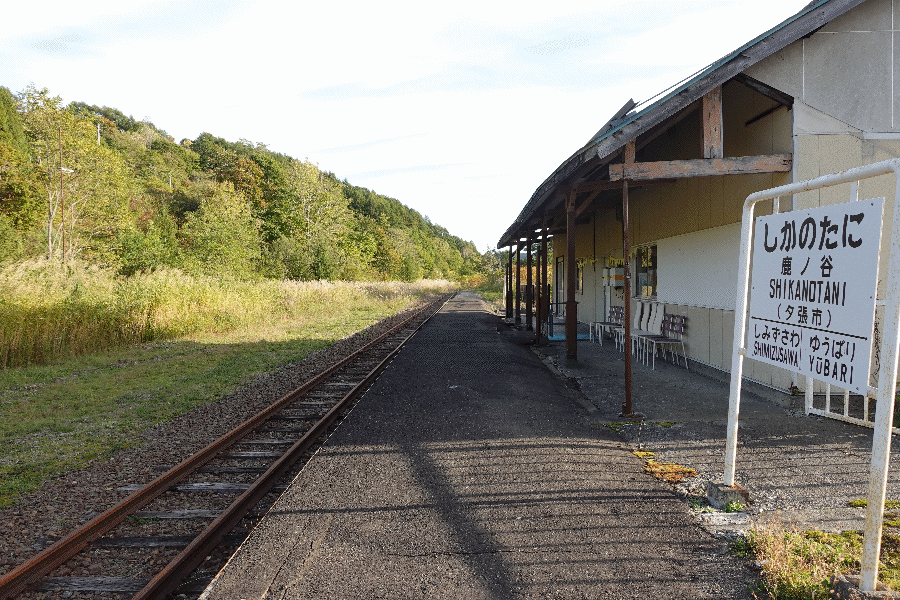


コメント