■はじめに
新しい旅のテーマとして、「比較的大きな町なのに鉄道が通っていない」ところへ訪問することを始めてみたい。
私の旅行は鉄道旅行が多く(時折レンタカーを借りたりもするが、レアケース)、どうしても鉄道沿線が観光対象となってしまう。駅から遠い観光地であると、どうしても足が遠のいてしまう傾向がある。
例えば、鉄道が廃止になってしまうと、訪問する頻度がめっきり減ってしまう。そこで、そのようなご無沙汰な場所に行くシリーズとして、「駅のない終着駅へ」シリーズを開始して旅行を行っている(これまでに、三段峡や加津佐、輪島などを訪問している)。
そして、そもそも論として街の中心部に鉄道がないと、ご無沙汰どころか、全く行っていない場所も多くある。そこで、「鉄道がない街」を意図的に訪問することにしてみた。
記念すべき第1回目は、宮城県登米市にした。なお、鉄道がない市町村についてまとめたウェブサイトなどもあるが、それらのリストには登米市は掲載されていない。というのも、登米市で地図検索をすると一目瞭然であるが、市の西部ギリギリには東北本線が掠めており、また南部ギリギリには気仙沼線があるからである。しかし、市役所などがある中心部は、鉄道とは全く無縁の場所なのである。よって登米市の中心部は未だに観光したことがないため、今回初めて訪問することにしてみた。
■2025.9.30
5時台に家を出て、JRを乗り継いで大宮へ。そこから新幹線「はやぶさ」号に乗って仙台まで移動してきた。
ここからは、在来線を乗り継いで新田(にった)駅まで移動することとなる。鉄道が無い町に行くが、長距離移動は当然鉄道で移動である。
仙台駅で待ち構えていたのは、ラッキーなことにボックスシートの車両であった。
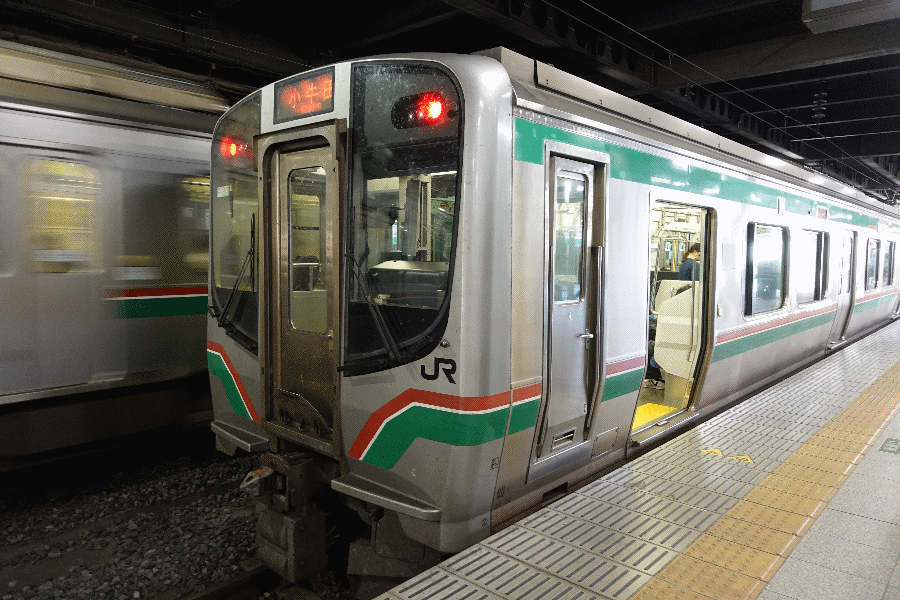
@前の方の車両はロングシートでしたが
定刻から1分遅れた8時12分に仙台を出発し、小牛田には8時55分に到着した。ここでしばし待ち、一ノ関行に乗り換えた。
9時06分に一ノ関を出発し、新田には9時24分に到着した。ここから、登米市中心部に行くバス(市民バス)に乗ることができる(ただし、運転本数はかなり少ない)。

@新田駅
しばらく待っていると、9時34分発のバスがやって来た。すでに乗っていた人も含めて、意外にも数人の乗客がいた。
行先の「佐沼」は、登米市役所などがある中心部の地名である。
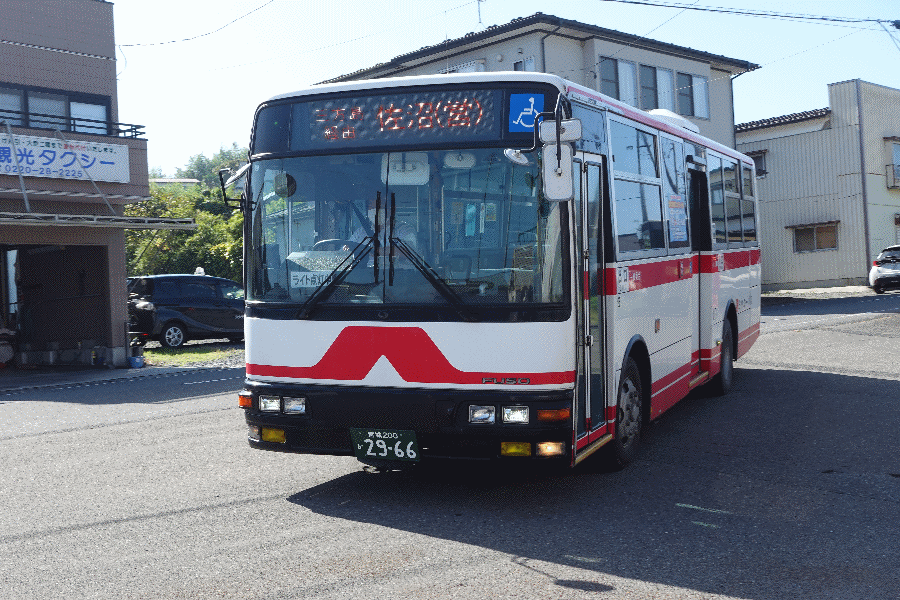
@市民バス
長閑な景色の中を走り続け、バスは中心部に向かって行った。市街地では、あちこち迂回をして行く。私は営業所までは行かず、市役所前で降りた。

@市役所
近くにあったスーパーで夜用食材の下見をしてから、まずはほど近くにある歴史博物館に向かった(拝観無料)。
この手の施設に来て、まず探すのは鉄道関係である。建物に入ると、いきなり仙北鉄道(JR瀬峰駅から登米方面に繋がっていた鉄道。1968年に全線廃止)の資料が展示されていた。
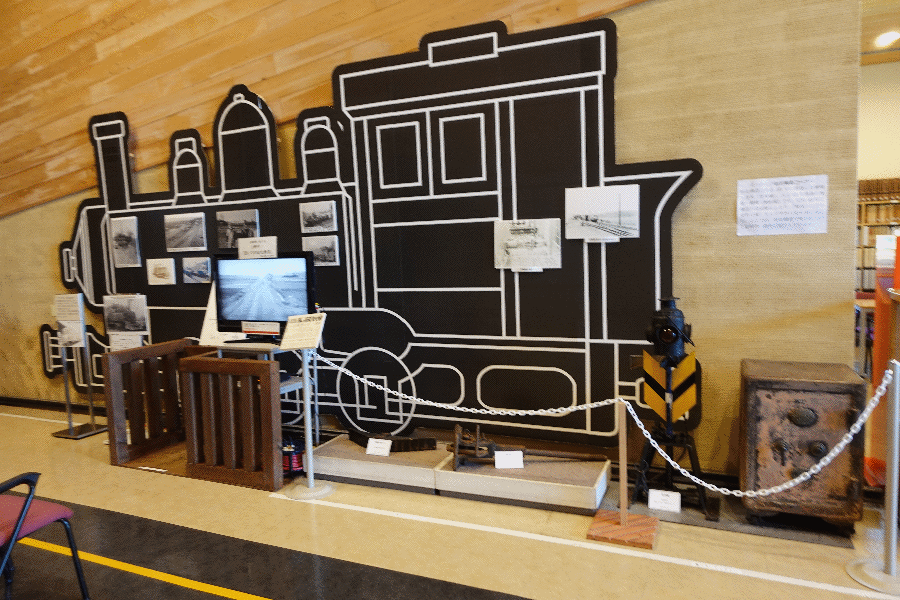
@鉄道関係資料
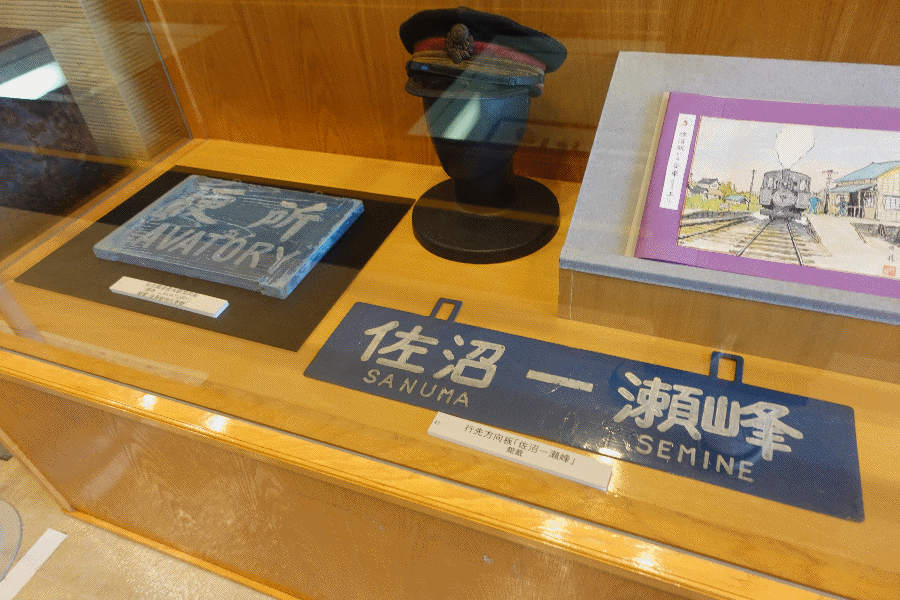
@行先標などもあり
その他の資料も見てから、近くにある旧居を見たりした。
続いての目的地は、「石ノ森章太郎ふるさと記念館」である。路線バスも無くはないが、本数が少な過ぎるため、歩いて向かった。
約50分歩いて、やっと記念館に辿り着いた。この辺りは、地名自体が「石森」である。漫画家の石ノ森章太郎氏(初期の頃は「石森章太郎」)は、章太郎だけが本名で、苗字は地名から来ているのである。

@石ノ森章太郎ふるさと記念館
石巻にある石ノ森萬画館には行ったことがあるが、こちらは初訪問である(アクセス手段が良くないため)。
700円を支払い、あれこれと展示品を閲覧した。写真撮影は不可であるが、1つだけ撮影スポットがあったため、それを写真に収めた。
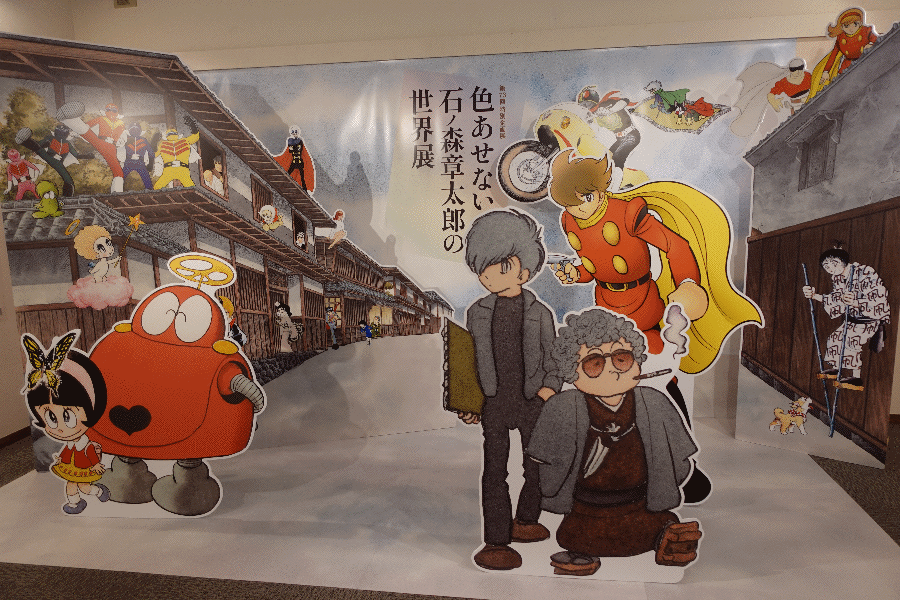
@撮影スポット
それにしても、石ノ森氏が亡くなったのが60歳であったとは。人はいつ死ぬかわからないから、私も出来ることは早めにしなければならない、と思った(例えそれが遊びであっても)。
記念館を後にしてから近くにある「石ノ森章太郎 思い出の小路」を歩いたりして、続いて向かったのは生家である。こちらは、無料で見ることができる。

@生家の中
生家を見学してからは、往路とは違う道を遠回りして中心部に向かって行った。というのも、「産直なかだ愛菜館」という場所に行って地物を探そうと思ったからである。
ひたすら歩き続けてその場所に辿り着いたが、なんと今日の12時から、臨時で「システム調整」ということで休業とのことであった。
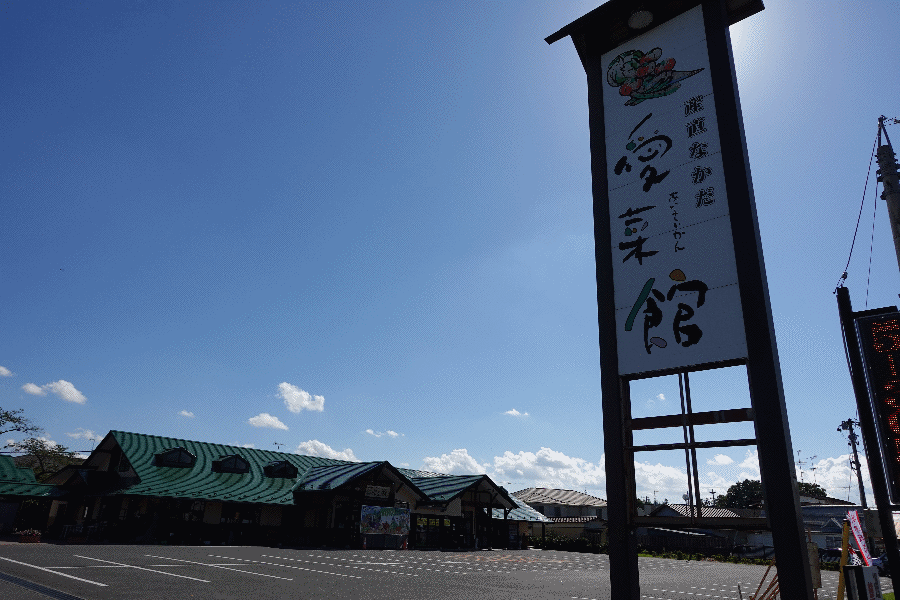
@無念
代替の品々を探すべき、その後は中心部にあるスーパーを3軒ほど周って地物を探した。テーマは「登米市内で造られているもの」である。
あれこれ買ってから、予約済である安ホテルに向かった。
買い揃えたのは、登米市で造っている納豆、練り物、そして「しそ巻」である(ピーマンは、家に持って帰る用)。

@戦利品
そして特異的であったのが、通常の8倍くらいありそうな大きな油揚げである。調べてみると、第3代横綱丸山権太左衛門の里米山で生まれた品であるとのこと。単体では大きさが分からないため、JRの切符と並べて撮影してみた。
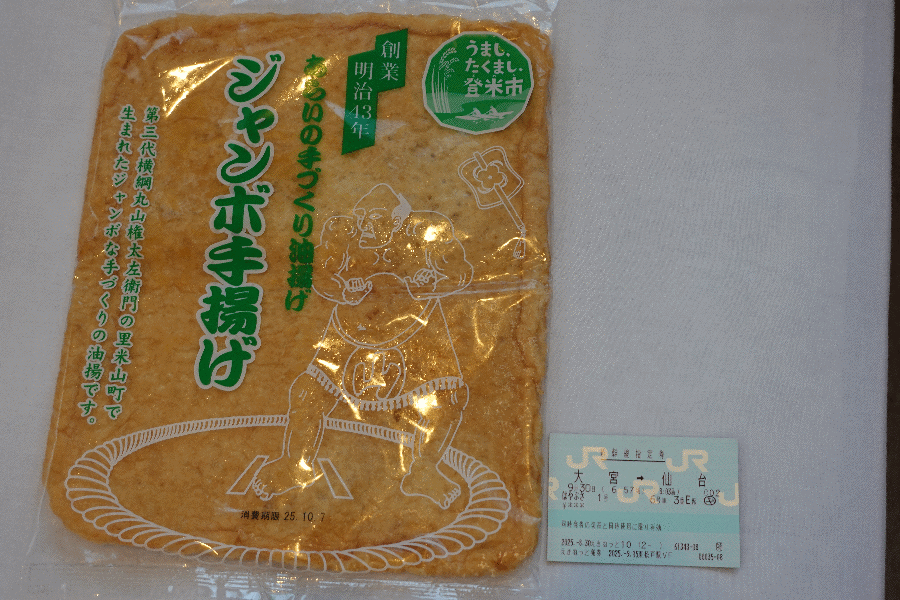
@大きな油揚げ
日が暮れてからはそれらで一献して、この日は終了である。
■2025.10.1
今日は、残念ながら雨模様である。8時頃にホテルを出て、バスの始発である佐沼営業所までやって来た。
これから乗るのは、8時23分の登米三日町行である。
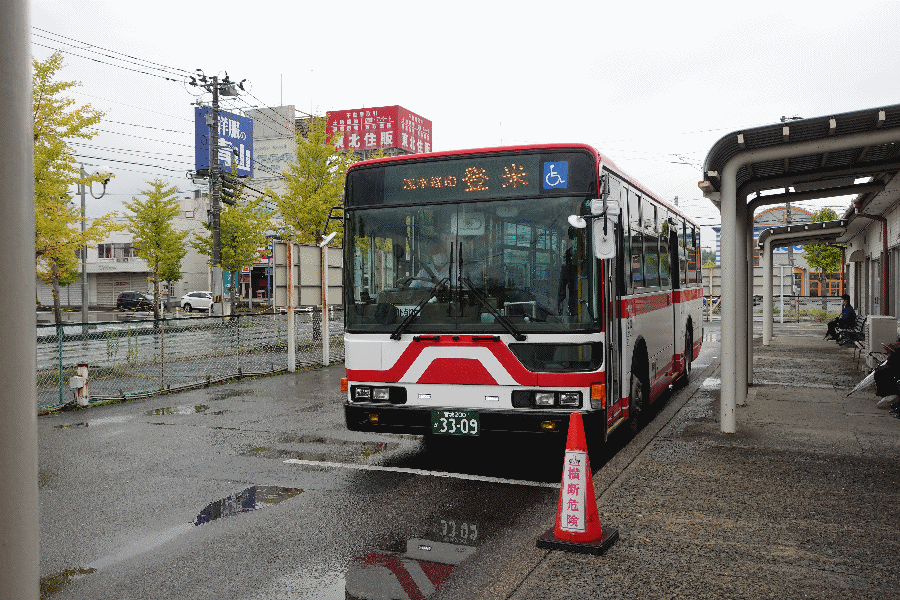
@今日はバスから
定刻に営業所を出発。通勤通学で多くの人が乗るのかと思っていたが、最初から少人数で、米谷(まいや)病院前で最後の乗客が降りてしまった後は、ずっと私1人だけであった。
9時19分、終点の登米三日町に到着した(1時間弱も乗っていたが、市民バスはどこまで乗っても200円均一である)。登米市については、中心部よりもこの辺り(登米市登米町)の方が、観光要素が多い。

@廃校を利用した教育資料館(昨日買った「しそ巻」の写真)
なおこの辺りは上述した通り「登米市登米町」であるが、読み方は「登米(とめ)市登米(とよま)町」であるから、ややこしい。
続いての訪問は、すぐ近くにある物産館である。この地域で有名な「あぶら麩」を購入した。

@登米で造られている品
なぜこの地域に観光要素が多いのかというと、「みやぎの明治村」ということで、武家屋敷なども多くあるからである。資料館系もたくさんあって、時間が足らないくらいである。

@趣のある壁
鉄道ネタは無いと思っていたが、無料で見られた「玄昌石の館」というところに、トロッコ車両が置いてあった。
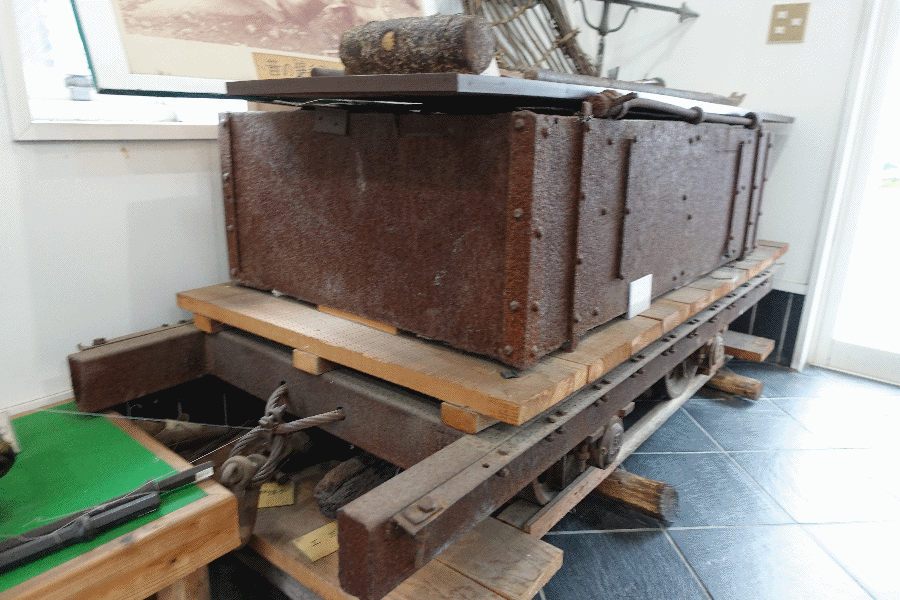
@一応鉄ネタ?
観光を終えてからはJRの柳津駅に移動するが、バスの本数が少なすぎるため、1時間半くらい掛けて歩くことにした。
歩くこと自体は問題ないが、今日は雨が降っており、しかも線状降水帯がすぐ近くに来ている。それが東に移動してくると大変なことになるが、幸いにも北へ移動してくれた。
てくてくと歩き、柳津駅に到着した。

@柳津駅
東日本大震災前まではこの駅より北へも鉄路が伸びていたが、今はその部分はBRT(バス高速輸送システム)になっている。
駅前にBRTの車両があったので近づいてみると、前部に「実験中」とある。近くにあった看板を見てみると、どうやら自動運転の走行試験をしているようであった。
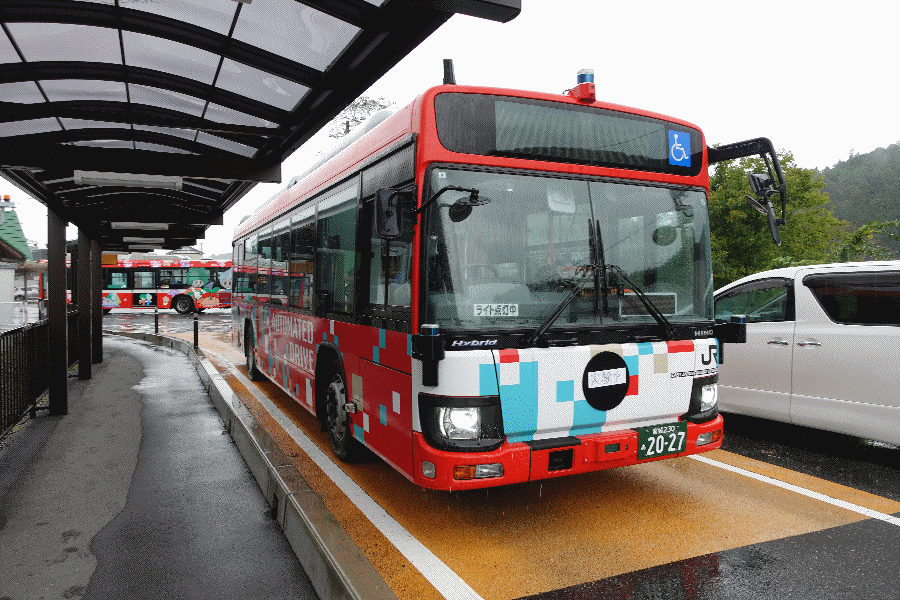
@走行試験中のバス
ここからは、11時30分発のJRに乗り、前谷地で乗り換えて、その先は小牛田と仙台で乗り換えて、最後は新幹線に乗って帰路に就くだけである。
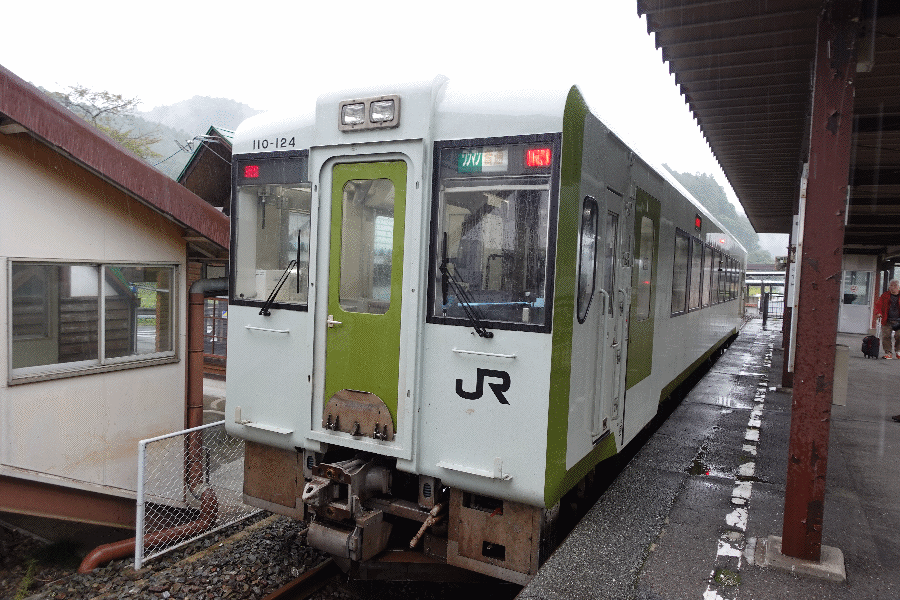
@最後はまた鉄道に
…という感じで終わる予定であったが、先述した線状降水帯により、東北本線が止まってしまっていた。よって、小牛田で足止めである。
しかし、乗り放題のパスを持っているのが私の強みである。ここから陸羽東線に乗って古川に行き、そこから新幹線に乗ることにした。「やまびこ」であるから自由席でも大丈夫そうであるが、「会話ができる」券売機で指定券変更ができたため、これですべて問題なしである。
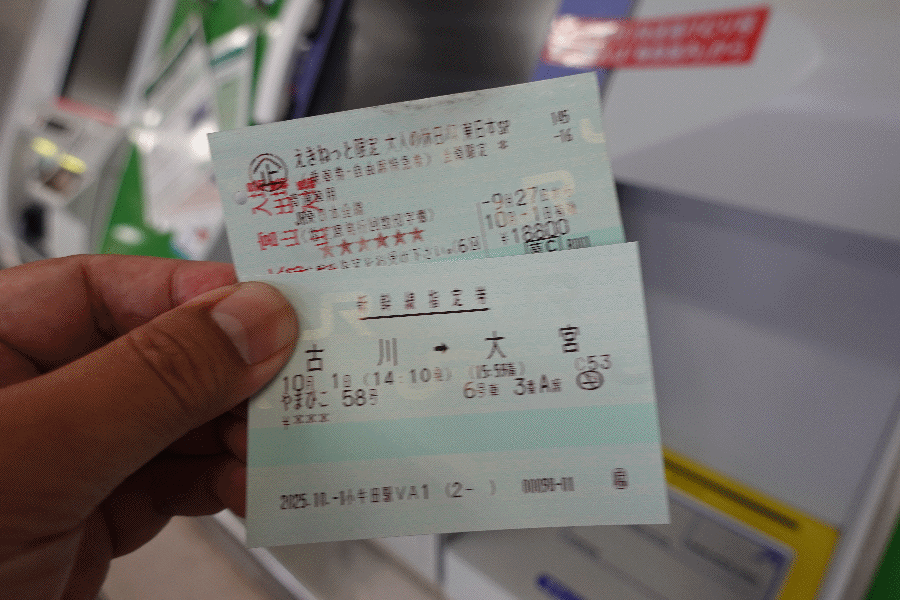
@これで帰る


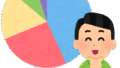

コメント