■はじめに
鉄道が廃止されたことにより「ご無沙汰」となった終着駅に訪問するこのシリーズであるが、6回目の今回は、JR東日本岩泉線の岩泉駅を訪問したい。
なおこれまでのシリーズで訪問した駅は本当に「久々に」来たところが多いが、岩泉については、実はそれほどでもない。というのも、近くに「ブルートレイン日本海」という昔の寝台車両を再利用した宿泊施設があり、そこに泊まるために2回ほど来たことがあるからである。
また、大人の休日倶楽部パスの残り2日分を使って追加の旅行もすることにした。切符の4日目は「新潟に行ってカレーを食べるだけ」の旅で、5日目は「銚子に行って醤油工場を訪問するだけ」の旅である。
■2025.6.24
十和田市への終着駅跡訪問を終えて、三沢駅に戻ってきた。岩泉線訪問は明日の予定であり、今日はこれからJRと三陸鉄道を経由して宮古に移動して、安ホテルに宿泊するだけである。
11時40分発の快速列車に乗り、八戸到着は11時58分。12時24分発の久慈行はすでに対面のホームに入線していたので、そちらに移動した。
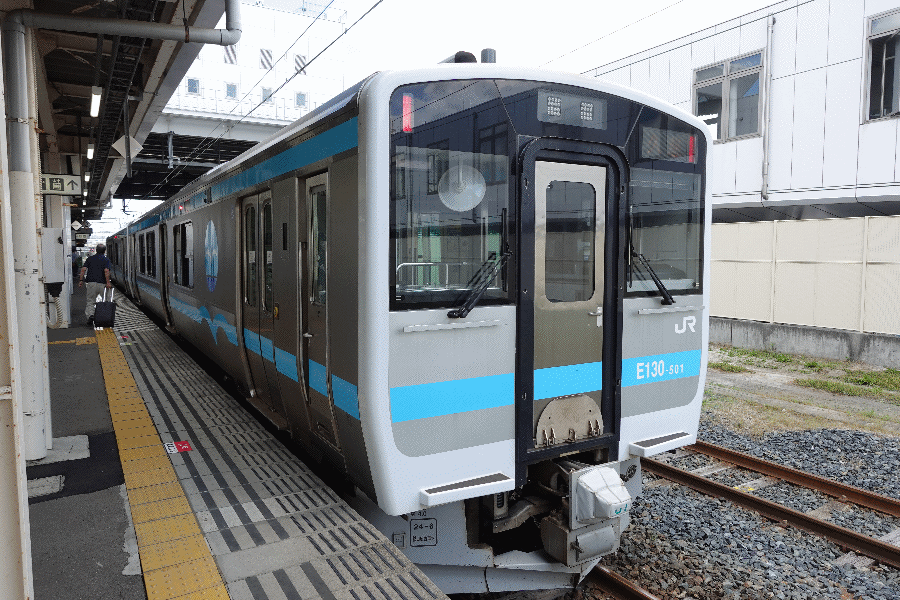
@これで久慈まで
座席を確保してから改札を出て売店で買い物をして、再度列車に戻ってきた。出発間際になると、席に座れない人も多数いるくらいの混雑となった。学生もいるが初老の旅行客も多く、昨日が大人の休日倶楽部パスの使用可能開始日であることも影響していそうである。
定刻に八戸を出発。旅のお供は売店で買ってきた南部せんべいであるが、例のパスがあると駅の売店(NewDays)が10%割引となるのが有難い。
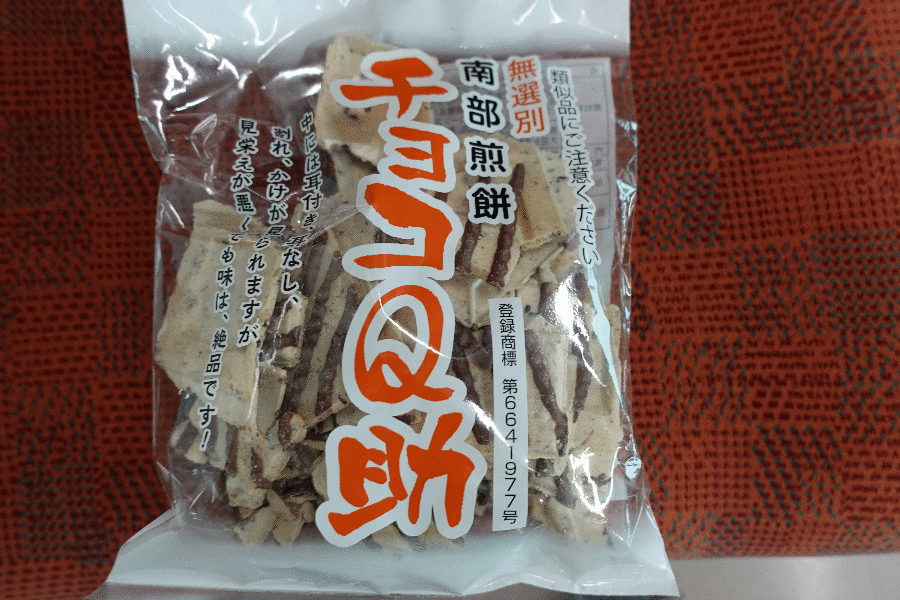
@お菓子
学生は近場の駅で降りていくが、高齢の旅行者はなかなか減らない。
ウミネコで有名な蕪島を過ぎると、左手に太平洋が広がって来る。今日は曇り予報であったが、あまり天気は悪くならずに済んだ。
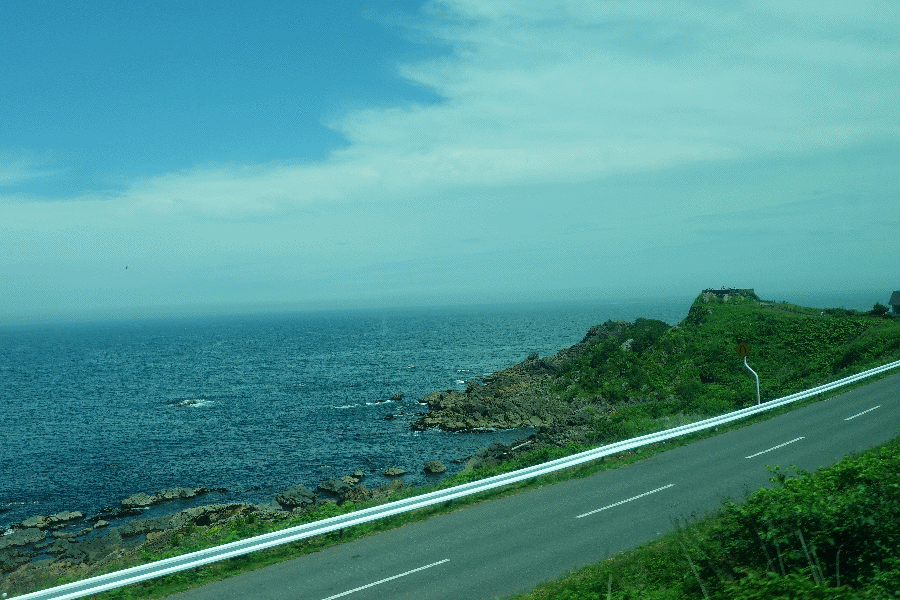
@海
ぼんやりと美しい景色を見ているうちに、定刻の14時09分に久慈に到着した。乗客の多くは接続する三陸鉄道のホームに移動したが、私はそのまま駅を出た。というのも、道の駅に併設されているスーパーで地物の魚を買うためである(詳細後述)。
余った時間は道の駅のフリースペースで休憩してから駅に戻り、16時14分発の三陸鉄道に乗り込んだ。

@宮古行
三陸鉄道は開通が比較的新しいためトンネルが多く、海が見られる場所は限られている。しかし、曇り予報はどこへ、さらにどんどんと天気が良くなっていったため、所々で絶景を拝むことができた。
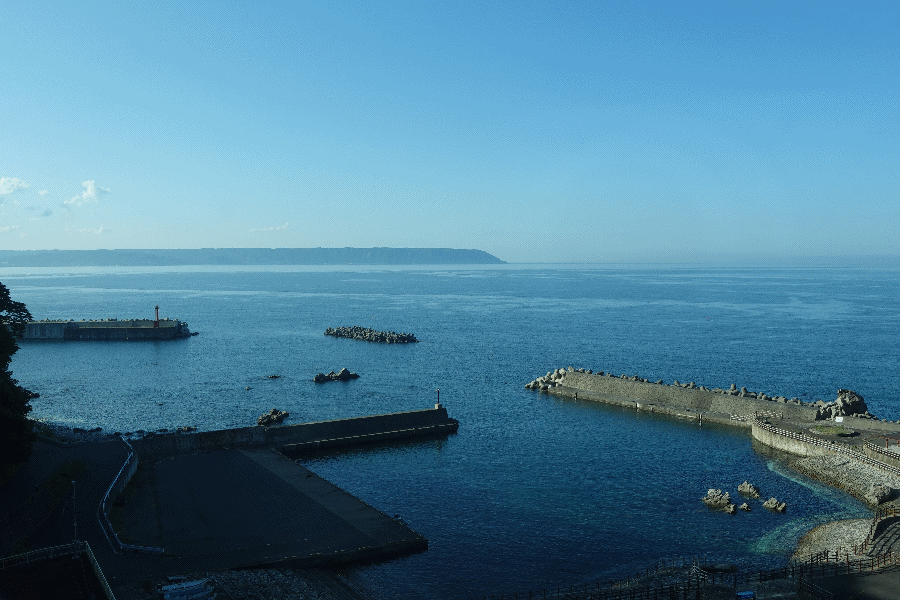
@天気良し
17時45分、宮古に到着した。ドラッグストアで酒を買い揃えて、安ホテルにチェックイン。
さて、夕食は久慈で買い揃えた魚で一献である。焼き魚(どんこ)と、久慈産のイナダと琥珀サーモンの刺身である。「サクで買ってどうするのか」と思われるかもしれないが、飛行機に乗らない旅で港町に行く場合は、小さな包丁を持参しているのである。
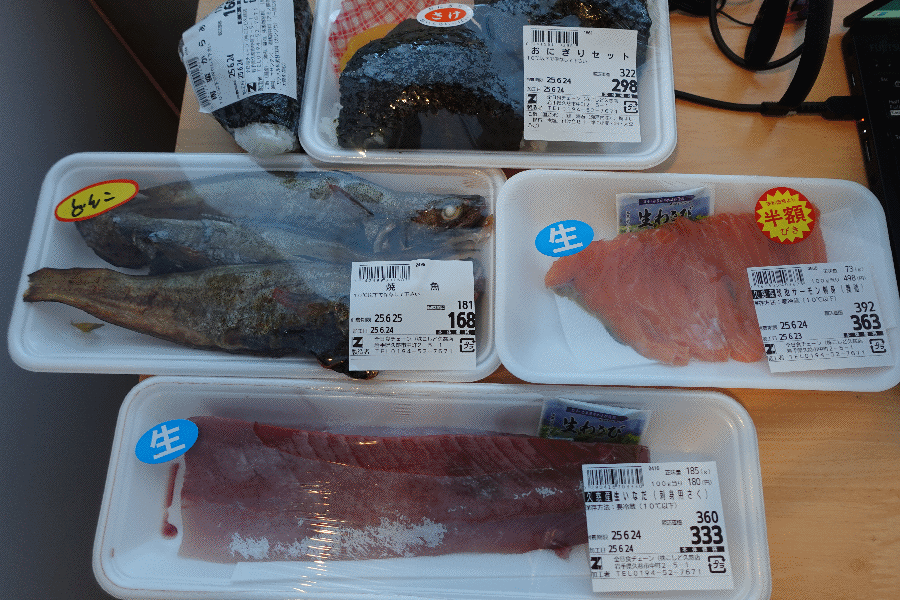
@これらで酔う(それにしても安い)
■2025.06.25
朝は7時くらいに出発するのがちょうどよいが、岩泉線の代替バスと山田線の茂市以西の運行本数が絶望的に少ないため、今日は5時過ぎにチェックアウトである。何せ、宮古発の山田線は1日に5本だけであり、そのうち盛岡まで到達するのは3本だけである。岩泉線代替バス(岩泉茂市線)も、全区間を通して走るのは3往復しかない。
駅に行き、改札を通った。JR乗り場には行かず、昨日の到着時に気になったものの撮影である(宮古には何度も来ているのに、気づかなかった)。
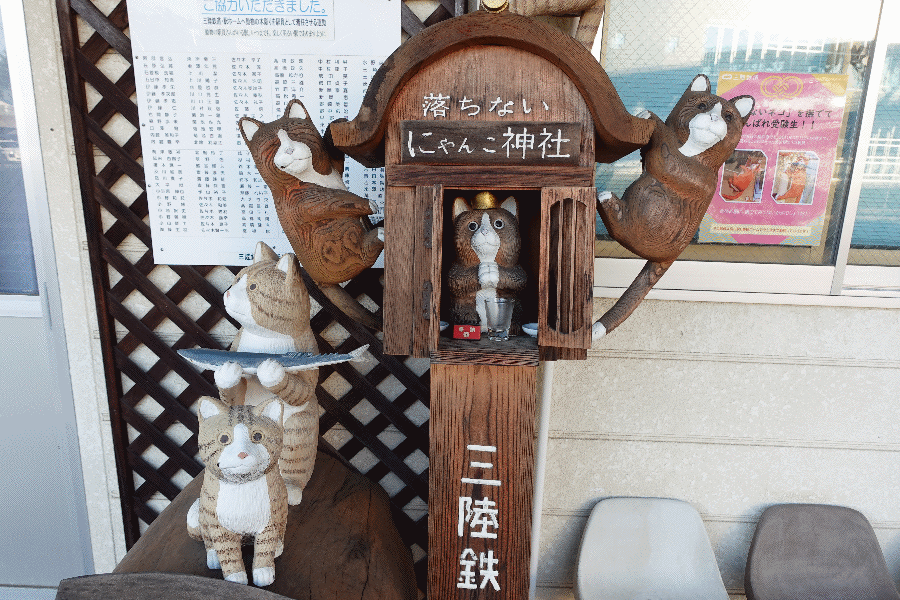
@にゃんこ神社
5時23分発の山田線に乗り込む。定刻に出発したが、乗客は私を含めても2人だけであった(昨日までのパターンで、乗客が少ないことにはもう慣れてきているが)。
しばらくすると、山田線利用に関するアンケートが係員より配布された(粗品はウェットティッシュ)。県北バスとの共同運行(JRの切符でバスにも乗れるが、フリー切符等は適用されない)についての質問もあったので、「フリー切符でも利用できるとよい(JR四国では使えます)」と書いておいた。
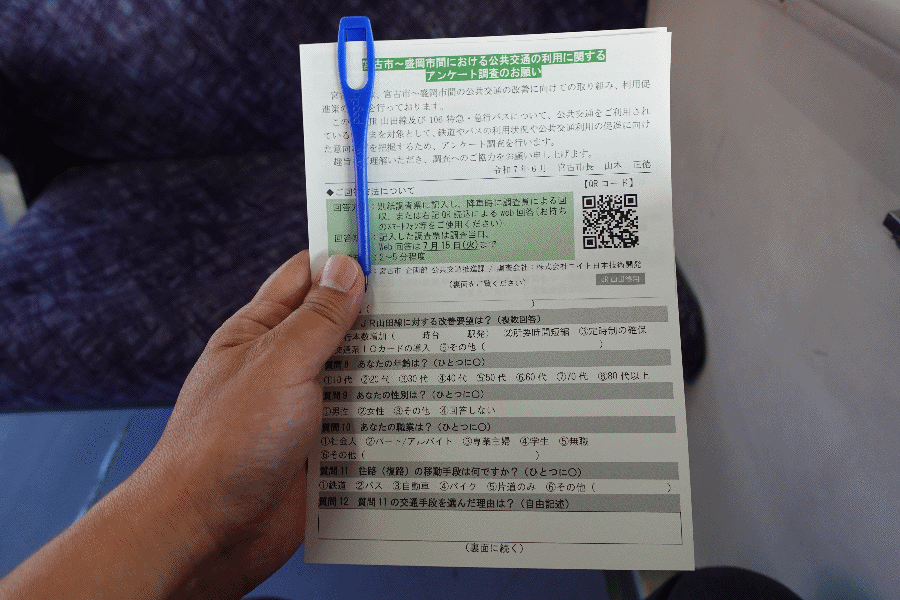
@アンケート用紙
5時46分、茂市で下車した。ここが、岩泉線が分岐していた駅である。
今から30年くらい前、貧乏野宿旅行をしていた際に、この駅で寝たことがある。当時はハンディサイズのポータブルテレビを持っていたのだが、この付近は山に囲まれているため電波が入らず、ほとんど映らなかった記憶がある。その思い出のある駅舎は取り壊されて、新しい駅舎になっていた。
岩泉線に使われていたであろうホームは、柵で覆われて入れなくなっていた。

@岩泉行が発着していた場所
バスの出発時刻は6時15分である。古い昭和的な看板の残っている駅付近を散策して戻ってきたが、出発までまだ20分もあるというのに、すでにもうバスがやって来ていた。
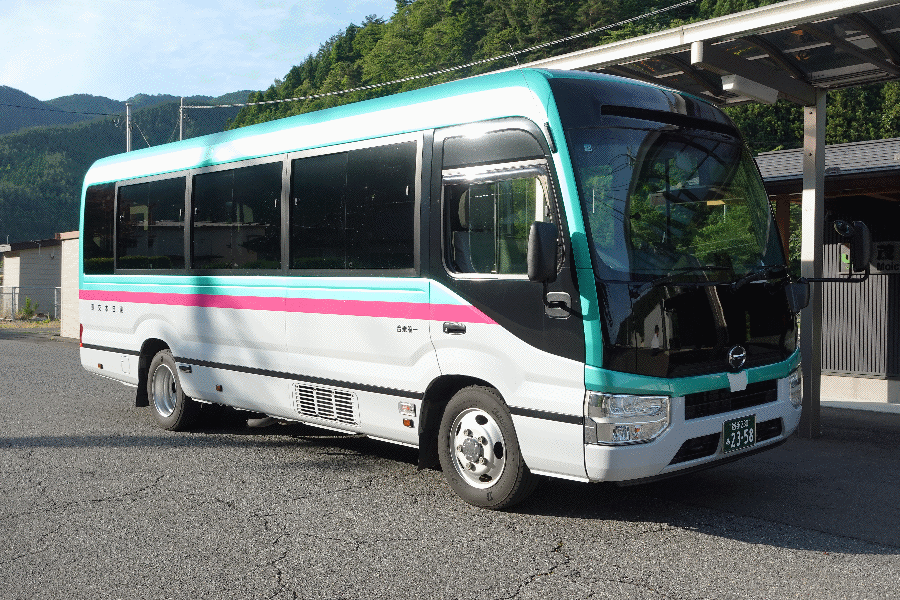
@代替バス
まだバスに乗るには早いため、駅付近を適当に散策した。鶯の鳴き声だけが響き渡り、長閑な雰囲気である。近くに商工会議所の支所があり、そこに岩泉線跡を利用したレールバイクの宣伝が貼ってあった。惹かれるが、どうやら2人乗りと4人乗りしかないようである。
駅舎の隣には、蜘蛛の巣だらけになって明らかに使用されていない乗務員休憩室が残されていた。岩泉線が現役であり、各列車にもれなく車掌がいたような時代には、このようなものが必要であったのだろう。
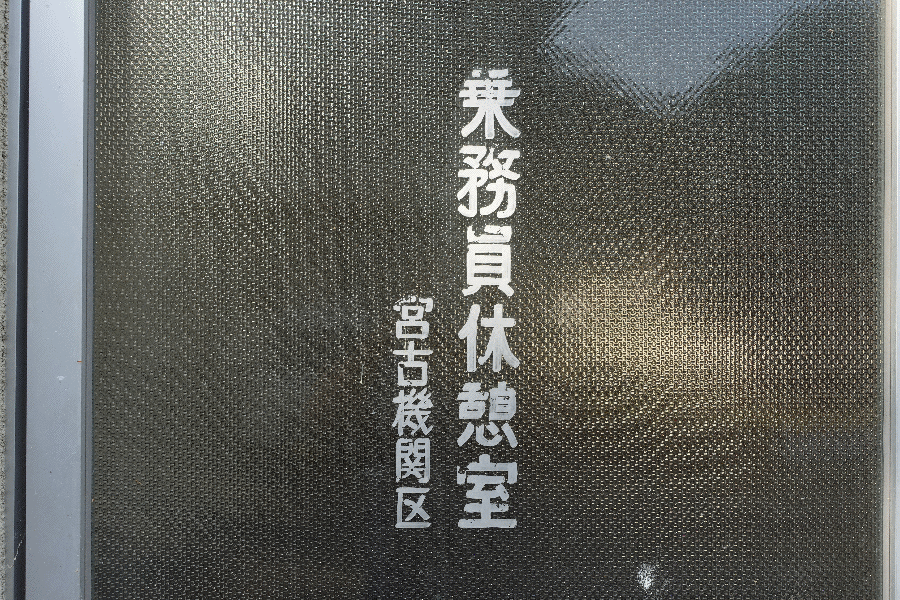
@今は廃墟
定刻の少し前にバスに乗り込み、茂市駅前を出発した。書くまでもないかもしれないが、乗客は私1人のみである。
しばらく走ると、左手に路盤が見えてきた。その後も路盤とは近づいたり離れたりしていたが、和井内駅(岩手和井内駅)に近づくとレールも見えてきた。ここは今、先述したレールバイクの基地となっている場所である。
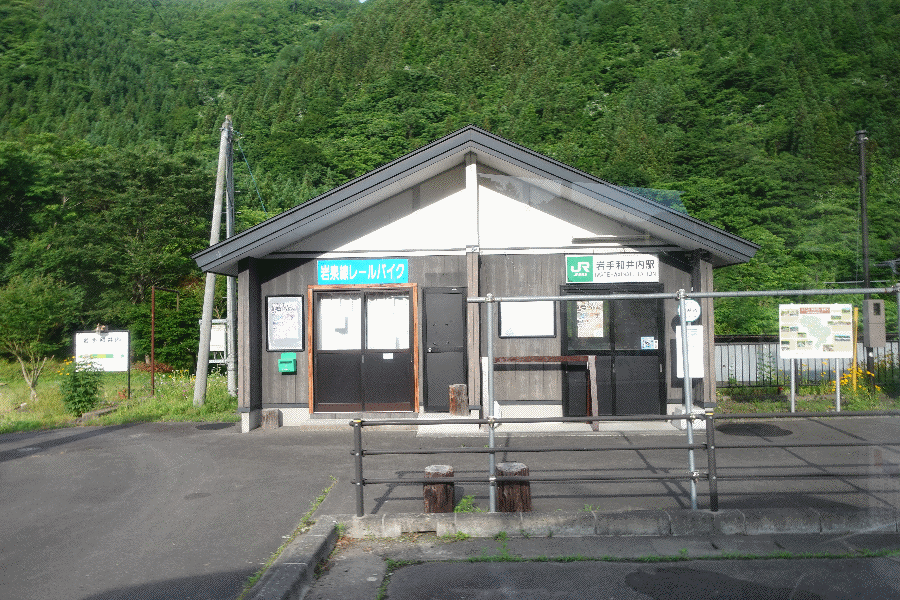
@再利用中
山深くなるにつれて岩泉線の路盤は鉄橋とトンネルでショートカットをするが、道路の方はそこまで整備されていないため、だんだんと道が細くなりスピードも出せなくなっていった。こういう山間部こそ鉄道の強みが活かせるのであるが、災害に遭ってしまったのは仕方ないし、そもそも目的地(岩泉)は大都市でもなんでもないので、そのような強みがあってもどうにもならないのである。
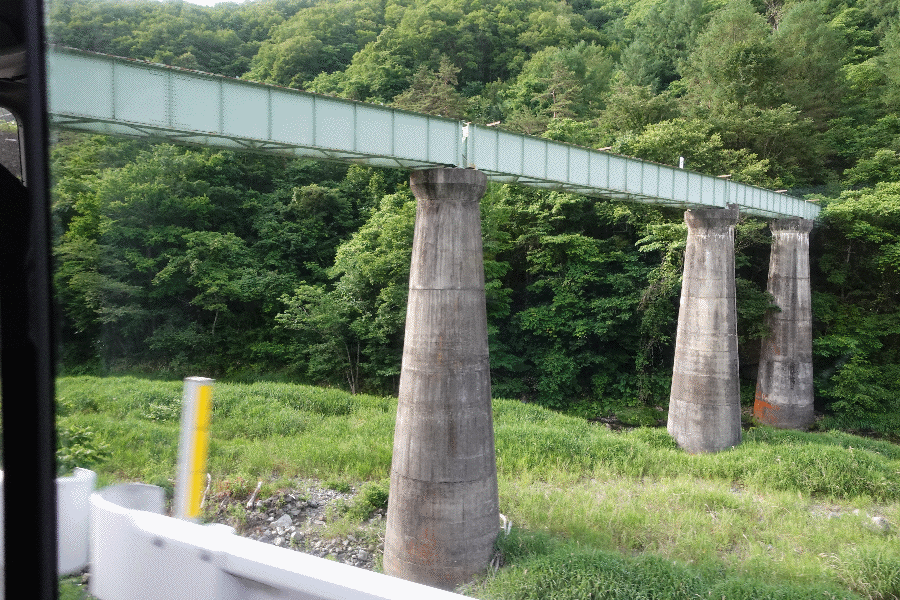
@時間短縮には橋とトンネルが必要
途中で1人だけ乗客が増え、山間部を抜けてやっと道路が広くなり、7時32分に到着した岩泉橋バス停で下車した。ここが、岩泉駅跡に一番近いバス停である。
歩いて駅跡に向かう。道路を渡ろうとしても、なかなか車の流れが途切れない。つまり、交通の流れは横(盛岡から直接岩泉を経由して海に至る)であり、縦である岩泉線のルートは交通のメインではないのである。数分歩いて、駅跡に到着した。
ローカル線の終着駅としては意外に大きな建物であるが、現在は2階には商工会が入っているという。
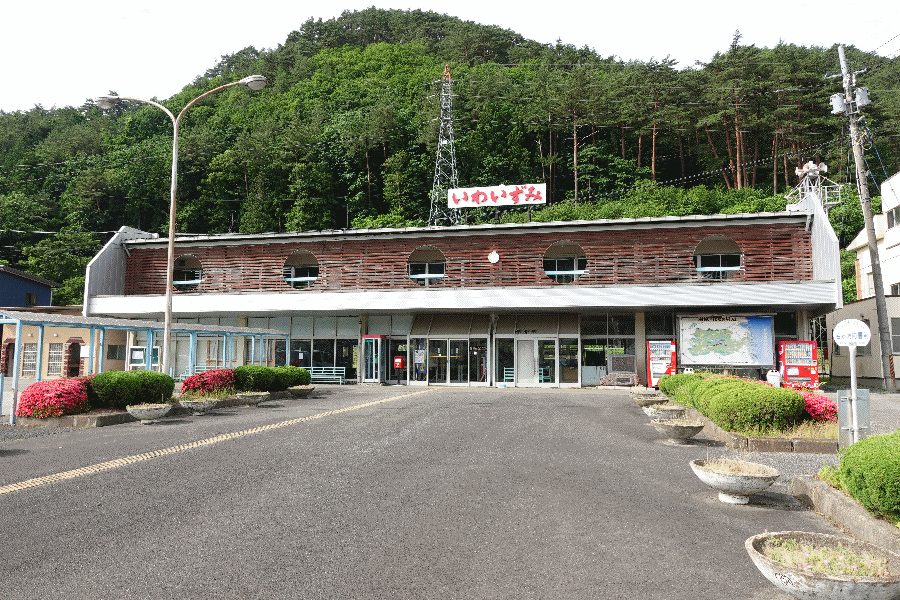
@現在の様子
私が岩泉線に乗車したのは、1998年の3月である。駅舎自体は当時も今も変わらないが、駅2階部分にある「乗って守ろうみんなの岩泉線」の標語が残念でならない。
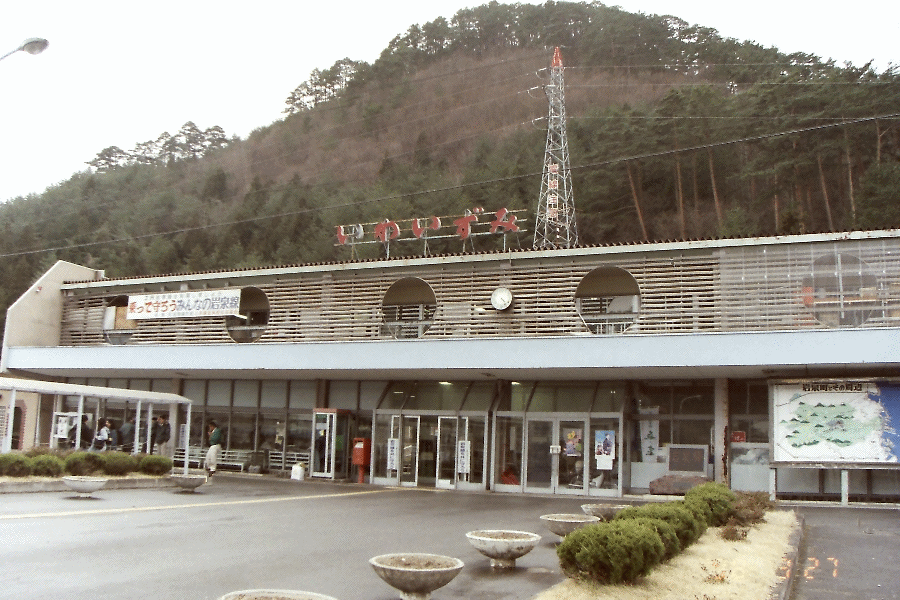
@守れませんでした
駅舎の裏手に行ってみる。ホームは残っているが、レールについては埋もれてしまったのか撤去されてしまったのか、駐車場として使用されている部分に少しあった以外は、見付けられなかった。

@表紙写真と似たような角度で撮ってみる
なおこの駅跡には2015年2月にも訪問しているが(例の「ブルートレイン日本海」に泊まるため)、当時はまだレールがしっかり残っていた。やはり、撤去済みということであろうか。
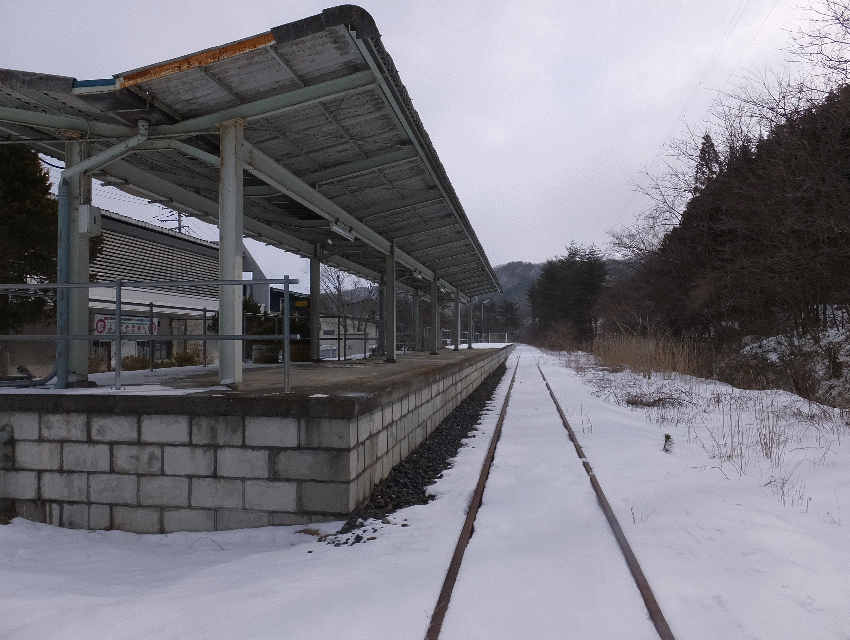
@まだレールがあった頃
駅前には古い観光案内図があるが、岩泉線があるのはもちろんのこと、国鉄の宮古線(宮古から田老まで)もあるのが懐かしい。
なお駅舎1階には岩泉線関係の展示物があるが、ドアが開くのは8時頃であるという。8時02分発のバスを逃すと次が16時52分になってしまうため、中を見学するのは諦めなければならない。
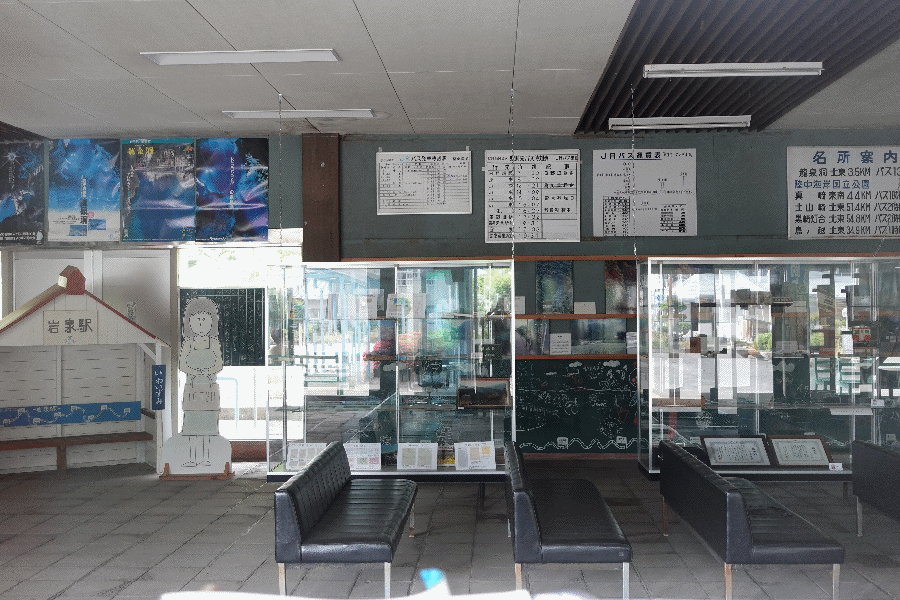
@外から覗くだけ
件のバスに乗って茂市に戻るため、バス停に向かって歩き始めた。すると、先ほどは商品皆無であった無人販売所に、野菜が並んでいるではないか。この手の販売所には弱いので、肉厚のピーマン(4個入り)を100円で買って帰ることにした。氷水で冷やして「パリパリピーマン」にでもする予定である。

@ピーマンお買い上げ
バス停から往路と同じ車両のバスに乗ったが、乗客はまたしても私1人だけである。しかし、このバスは1日に1本だけある「宮古病院行」であるため、途中から乗客は増えそうである。
往路と同じく、岩泉線の路盤跡と交錯していく。岩泉線の末端部分の開通は1972年と比較的新しいため、岩泉に近ければ近いほど立派な橋脚が残っている。

@立派
ちらほらと乗客が増え、茂市駅前到着時は6人に増えていた。茂市駅前で降りたのは私だけであるから、残りは皆宮古方面に行くようである。
まだ朝の9時台であるが、これから9時41分発の快速「リアス」で盛岡に向かい、そのまま帰ってしまう予定である(時間と切符を有効活用して、都内で野暮用を済ませる予定)。
■2025.6.26
さて今日からは、「余った2日分を使うだけ」の旅である。東京駅に向かい、7時04分発の新幹線「とき」に乗り込んだ。

@3種類揃い踏み
在来線の特急乗車時はぼんやりと外を眺めるが、新幹線だとどうにもそうならない(景色が流れるのが早過ぎる)。トンネルが多いこともあり、持ってきたPCで旅行記を作成したりして時間を潰した。
8時56分に新潟に到着し、10分ほど歩いてバスセンターに向かった。カレーを提供する店は、週末の昼時などはとんでもない行列であるが、平日の朝であるため並んでいる人は2人くらいであった。並(580円)を購入し、早速頂く。
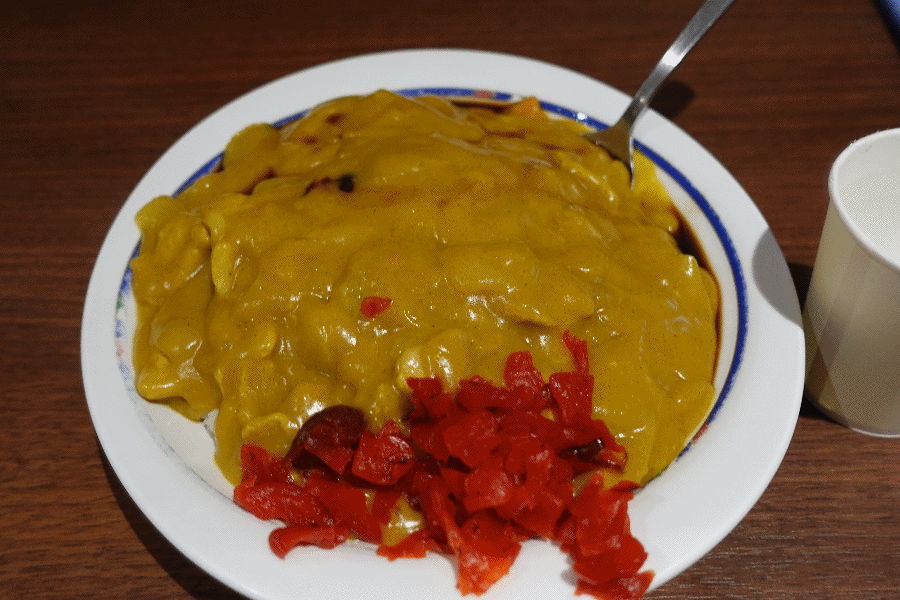
@バスセンターのカレー
小麦粉多めの昭和のカレーであり、それほど辛くないのだが、食べ終わる頃には首元に汗をかいてしまっている不思議な品である。
街中散策をしてから、駅に戻った。このまま家に帰ったのでは早過ぎるため、特急「しらゆき」に乗って高田に行って観光することにしている。
10時23分発の特急「しらゆき」であるが、念のため自由席に並んだが、1車両で乗客は数人しかいないくらいガラガラであった。
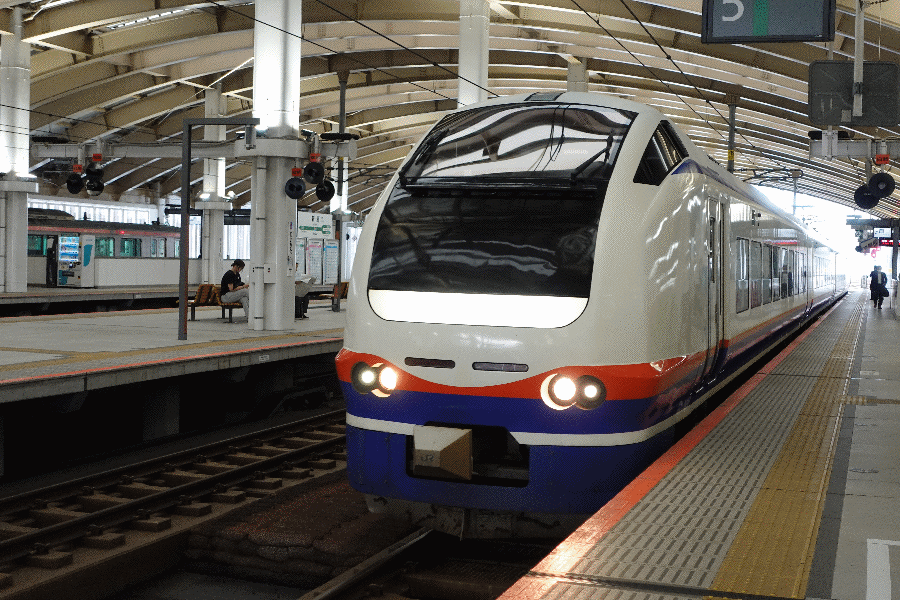
@しらゆき
定刻に出発。ガラガラの車内であるが、長岡までは新幹線があるため、混雑するのは長岡以降のはずである。予想通り長岡で多くの乗客が増えて、乗車率は5割を超えるようになった。
ぼんやりと景色を眺めるが、愛知から新潟に跨る長大な降雨帯が東に移動しており、私が高田に到着する頃にバッティングしそうである。
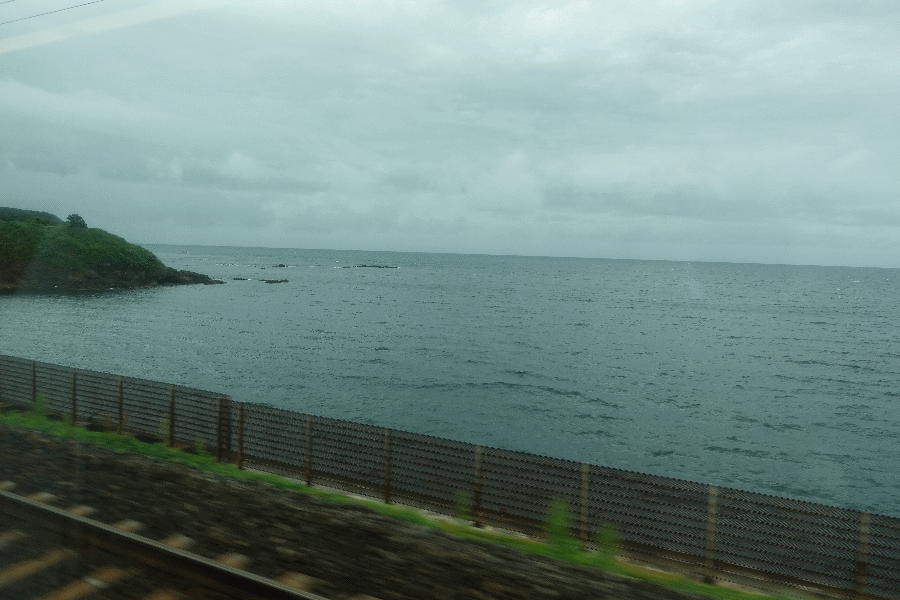
@青海川駅付近走行中
本来ならばどうしようかと思い悩むところであるが、今日は途中下車の時間を2時間以上も確保しているため、雨雲レーダーと相談してしばらく待合室で過ごすことにした。
定刻から8分遅れて、12時26分に高田に到着した。まさに降水帯が直撃していて豪雨であったため、待合室で40分ほど待ち、小雨になってから歩き出した。
まずは、古い街並みや観光施設の訪問である。
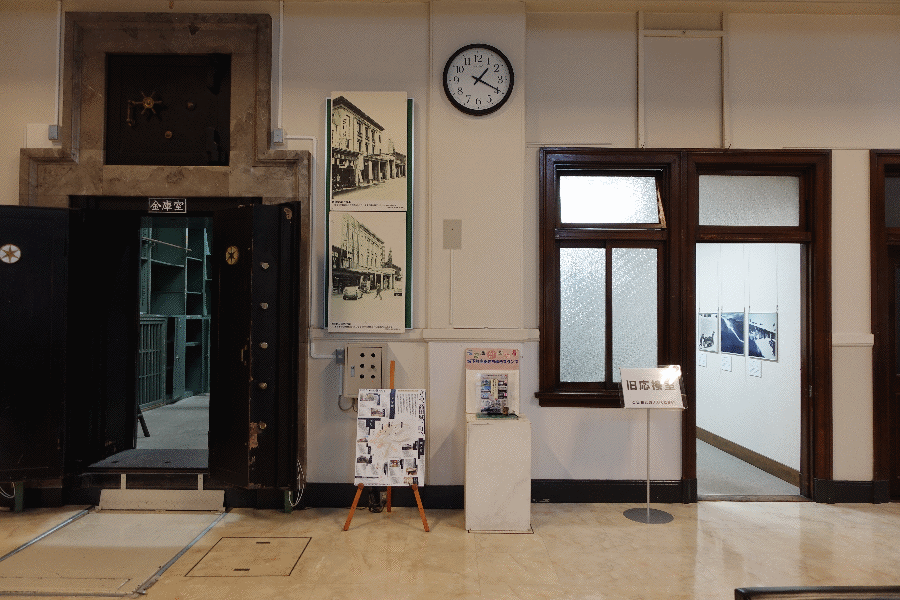
@銀行を再利用した施設(金庫に入れる)
雨も上がった中を歩いて、城址公園に向かった。ここのお堀は数多の蓮が有名であり、見ごろは赤い花が綺麗なのであるが、今はまだその季節ではない。ではなぜ来たのかというと、敷地内にある図書館に「小川未明文学館」があるからである。私は日本文学科卒であるが、児童文学には疎いため、来てみることにした。
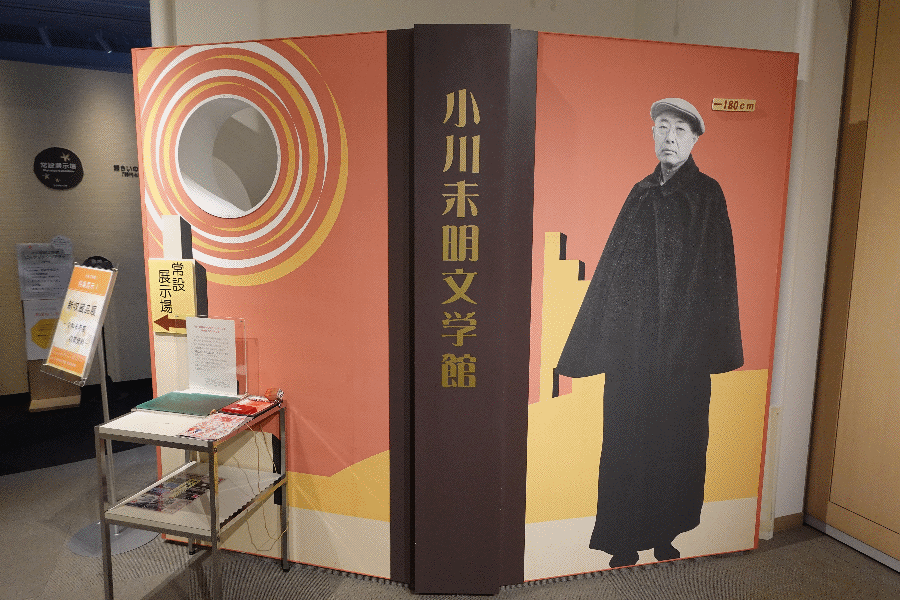
@無料で拝観できる
その後は古い街並みを経由して駅に戻り、14時43分発の列車で上越妙高に移動して、新幹線「はくたか」に乗って帰路に就いた。
■2025.6.27
昨日は「カレーの日」で、今日は「醤油の日」である。
7時台に最寄り駅からJRに乗り、乗り継ぎを経て船橋までやって来た。ここから特急「しおさい」に乗って銚子に行くことにしている。
詳細な乗車歴は付けていないが、房総半島の特急(「しおさい」「わかしお」「さざなみ」など。今は亡き「あやめ」などを含む)には乗ったことが無い。よって今日が、初めてである。
ラッシュ時であるため、ホーム上は大混雑であった。その中を、ゆっくりと「しおさい」が入線してきた。

@人が多いためこんな角度でしか撮れない
7時58分に船橋を出発し、列車は快走して行った。千葉県内のJRなど飽きるほど乗っているが、特急ですっ飛ばすのは楽しいものである。今後も同様に切符の利用期間が余った場合には、乗車経験のない特急「草津・四万」などに乗るのも面白そうである。
9時32分に銚子に到着。ヤマサの醤油工場までは、歩いて10分以内である。

@到着
この場所自体は以前に来たことはあるが、土日はビデオ上映のみ(工場内には入れない)であることと、コロナ禍中は見学自体を行っていなかったため、今回やっと見学できることとなった(なおネット予約が必須である)。
ちなみに、敷地内で最初に待ち構えているのは鉄道ネタである。現存する「日本最古のディーゼル機関車」である。
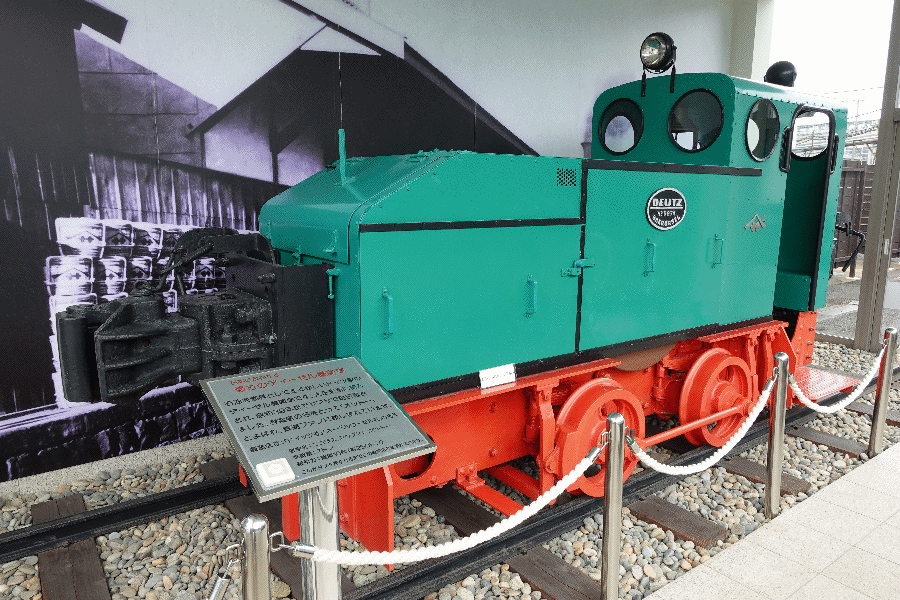
@ミニ機関車(工場内で使用されていた)
10時から15分程度のビデオを見て、その後は30分くらいかけて工場内を見学した(工場内は撮影禁止)。
終了後には、お土産を貰ってしまった(見学自体無料であるのに)。今日の旅は交通費も実質発生していないため、これで逆にプラスである。

@有難い
見学後は「利き醤油」などをしてから施設を後にした。
この後は11時46分発の列車に乗る予定であるため、1時間弱ほど時間がある。ということで、五重塔がある飯沼観音に行こうと思った。
歩き出して踏切を渡ると、銚子電鉄の仲ノ町駅がある。3編成係留しているところに定期列車がやって来たので、4編成揃ったところであった。
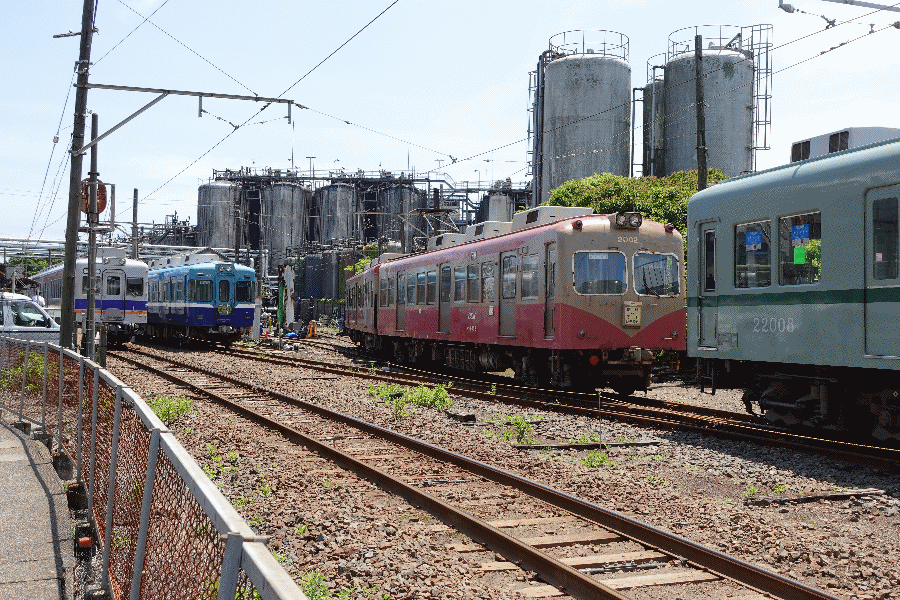
@勢揃い
飯沼観音を参拝してから駅に戻り、件の列車に乗り、成東と大網と上総一ノ宮で乗り換えて、勝浦までやって来た(14時18分着)。というのも、スーパーで地の物でも買って帰ろうかと思ったためである。
しかし、事前の下調べの段階で分かったのだが、勝浦駅付近にはあまり地元スーパーがないようであった。そこで、予定通りに御宿まで戻ることにした。14時59分に出発し、15時03分に到着。
せっかく御宿に来たので、とりあえず海岸まで行ってみる。
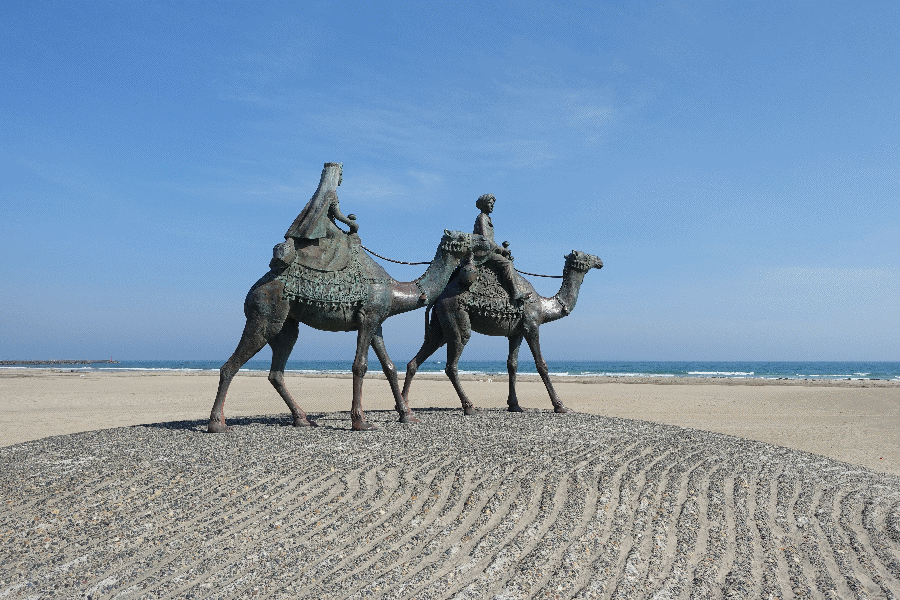
@月の~、砂漠を~♪
町内に戻って、地元スーパーに入った。勝浦産の刺身も数種類あるが、内陸部とはいえ私も千葉県在住であるため、そこまで珍しくもない。それに、自宅ドアまでここから2時間くらい掛かるから、氷をたくさんもらって運ぶのも面倒である。そこで色々と見て回ると、いわしの卯の花漬とごま酢漬を発見したので、それを買うことにした。ついでに、夷隅(いすみ)産の「おかわかめ」なるものも発見したので、追加購入である。
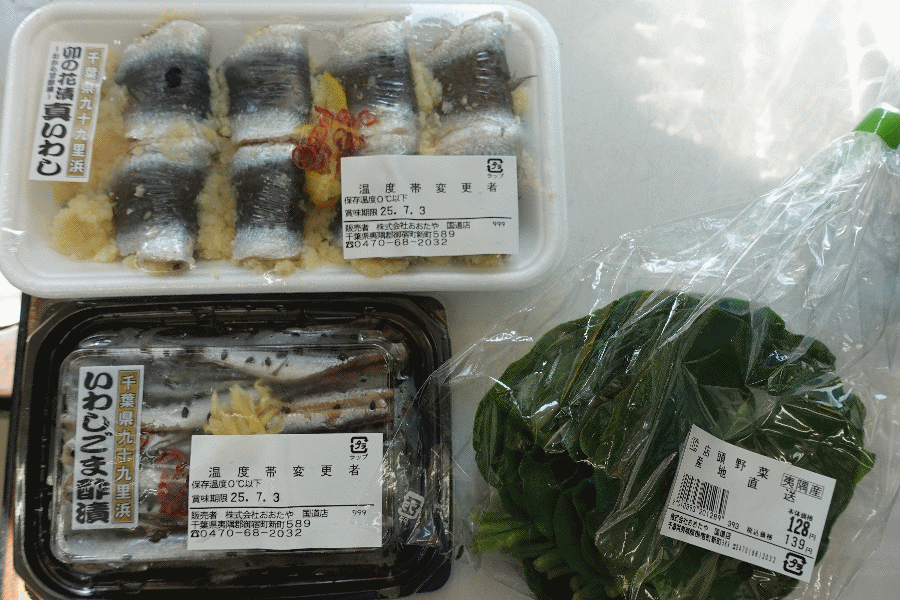
@戦利品
地元の品を得て、ほくほく顔で駅に戻った。この後は、16時12分発の特急「わかしお」に乗って海浜幕張まで移動し(もちろんこの特急も初乗車)、そこから乗り継いで家に帰るだけである。
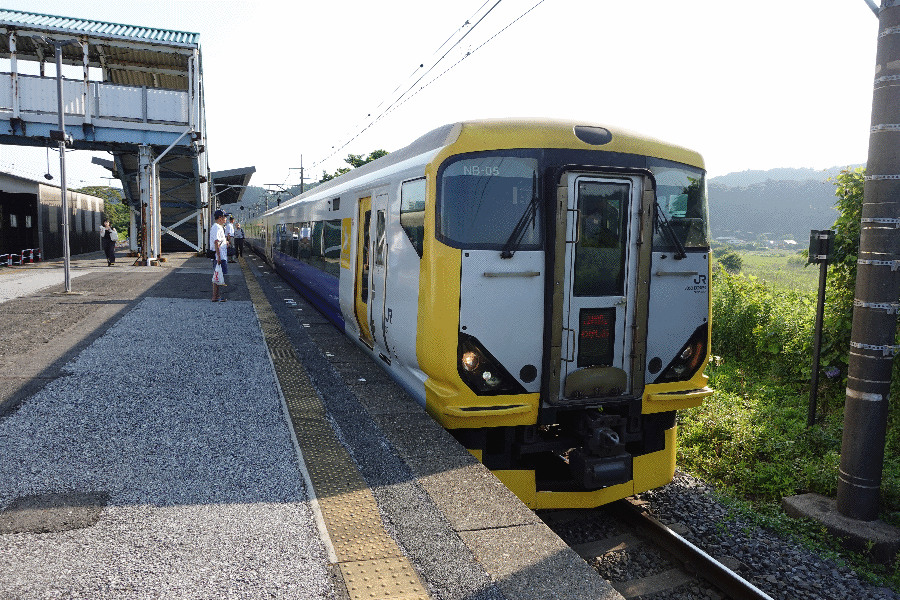
@わかしお
【過去のシリーズ】
駅のない終着駅へ Part1(三段峡駅)
駅のない終着駅へ Part2(加津佐駅)
駅のない終着駅へ Part3(おまけで「惜別・留萌本線」)(留萌駅・増毛駅)
駅のない終着駅へ Part4(輪島駅)
駅のない終着駅へ Part5(細倉マインパーク前駅・十和田市駅)



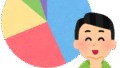
コメント